記事を読まれる前に「Social Good Circle」の申し込みをされたい方は、下記ボタンよりお願いします。
こんにちは。Social Good Circleの共同運営者をしている平畑です。
3月のSocial Good Circleは、3月26日(水)20:00から開催します。いつも金曜に開催しているのですが、以前参加されていた方々が別のイベントによって参加ができなくなっていることを念頭に、試験的に金曜以外の曜日で開催することとしました。曜日を変えることで、参加者の多様性が図れるようであれば、土日開催や時間の変更なども検討していきたいと思います。
さて、3月は「別れの季節」といいますね。卒業シーズンであり異動シーズンでもある。そして退職し新たな道へ進もうとする方もいます。2月のSocial Good Circleでは、ひと足先に『異動に関するモヤモヤ』についてダイアローグしました。「今までの部署で仕事を続けたい」「まだやり残したことがある」など、さまざまなモヤモヤが表出された一方、「モヤモヤの主語ははたして「異動」なのだろうか」という問いが出てきて、それについても活発なダイアローグが展開されました。参加された皆さんのモヤモヤの一部をご紹介します。

〇〇支援を8年やってきて、本音のところはもうちょっとやっていきたいと思っています。できれば異動したくないな。異動したらまた1から覚えんといかんやんって言うのもあるし。それに今の部署を長くやってきたこともあって、好きになっているんですよね。もっと工夫したいところもあるし。



私は2年おきに異動があって、以前働いていた部署とはまったく違う部署になると、それこそ1から仕事を覚えないといけない。引き継ぎ書を見てもわからないことが多いです。転職したような気分になりますよ。こういう異動を経験していくと、組織に対してとても憂鬱になりますし、そもそも支援を必要としている人たちの不利益になるとも思っています。



異動になる前に希望調査をする職場もあると思いますが、多くの場合が突然くる。そして「受け身」の立場が多いのかな。自分で希望出して、自分が納得している異動であれば、主体的に選んでいることになるから、モチベーションに違いが出てくるかも。
単に「異動」といっても、人によってさまざまな捉え方、価値観があります。「一から仕事を覚えていることに自信がない」「異動ばかりで先が見えない」など、ネガティブな印象を抱いている一方、異動を能動的に進めた人にとっては、逆にモチベーションが向上する場合もある。対話を深化させていくと、「私は苦手なことがあることを周りに伝えていた。そうすると助けてもらうようになった」という語りが表出され、苦手なことを内面に閉ざすばかりではなく、対話をすることで手を差し伸べてくれる”仲間”が出てきてくれたことにも気づきを得られました。
異動を主語にするというより、『「私」を主語にした異動』にすることによって、考え方にバリエーションが生まれることがわかりました。多くの方が異動を受動的なものとして捉えていますが、「私はこの部署で〇〇をしたい」とか「ここに配属されることで〇〇のようなことができるかもしれない」など、『私を主語』にすることで、異動が受動的なものから能動的なものへと変化するのだと思います。
Social Good Circleの中では、「受け身より主体的に物事を決められる、選択できることのほうがモチベーションが上がる」との言葉が訊かれました。『自分で決めた』という、選択することで一種の責任を抱くかと思いますが、決めるまでの過程で色々な葛藤や不安、それらを吐露できる人と場所があることで、モヤモヤが大なり小なり浄化され、前向きな『覚悟』を持てることにつながるのだと思いました。
とはいえ、全てにおいて能動的に自分で決められることばかりではありませんし、異動についてはやはりマイナスなイメージを持つ方も多いと思います。Social Good Circleではそれらについてジャッジはせず、参加者の多様な意見や考え方のダイアローグを通して、それぞれが何らかの『気づき』を得る時間を大切にしています。その中で、「異動をマイナスに捉えてしまうのは、そのときの自分の置かれている環境や心理状態次第のところもあるのでは」との語りを訊いて、あぁそうだよな、と共感の輪が広がったのは、今回のSocial Good Circleのハイライトの一つでした。「決して異動が嫌じゃなくて、異動と言われたときにセルフケアの状況はどうなのか」にスポットを当てると、『「私」を主語にした異動』に変化するのではないかと感じました。
そのためには、普段から心の余白を作っておくことや、ストレスを溜めすぎず、解消方法をイメージまたは取り組んでおくことが、急な辞令に対して対処できるのではないかと思います。これは支援を必要としているクライエントにも置き換えることができます。『人と環境の交互作用』を自身の経験や思いを語り合うことで、自らの支援にも派生できたSocial Good Circleになりました。
Social Good Circleは『助言も否定も解決もしない』ことを理念として掲げています。それでも対話が進むうちに、自自身のモヤモヤから支援者としてのアイデンティティに気づくことへ発展する場合があります。でもそれは解決を軸としておらず、参加者全員が丁寧に語りに耳を傾けること、そして自身も語ることを基盤としているからこそ、自然発生的に『私と支援者』との境界を行き来したり、取っ払ったりしているのだと思います。
Social Good Circleは誰もがフラットな関係性で、ご自身のペースで語ることができます。普段モヤモヤしていることがあれば、お気軽にSocial Good Circleへ参加されてみてください。
Social Good Circle 開催詳細
Social Good Circleには多くの方が参加しやすいように、オンライン開催としています。仕事から帰ってきてひと段落した時間帯にすることで、ゆったりと語り合えるようにしています。以下、開催詳細をご覧ください。
開催日
- 2025年3月26日(水)20:00〜21:30
参加方法
- オンライン(zoom使用)
申し込み後に招待URLを送らせていただきます。
参加費
- 無料
気軽に参加できるよう参加費はいただいておりませんが、今後対面で開催することも検討しています。
その際は参加費を頂戴する場合がありますのでご容赦ください。
申込方法
下記の「申し込みフォーム」と書かれているボタンをクリックすると、申し込むフォームへ移動します。
必要項目を入力していただき、送信後、開催に関するメールが届きます。
申込手順
まずは申し込みフォームの入力をお願いします。ご不明な点があれば、お問い合わせからご連絡ください。
Social Good Circleとは
Social Good Circleは「支援者のモヤモヤをダイアローグする場」としています。よって、参加者同士の上下関係もなく、全てがフラットです。日々の実践や人間関係など、モヤモヤしていることを語っていただき、聞く側は助言も否定もせず、ただただ訊くことに徹します。
もちろん訊いた後に、自らのモヤモヤを語っていただくことも大歓迎です。「今更こんなことは職場で話せない」や「誰か私のモヤモヤを訊いてほしい」など、Social Good Circleにおいては気楽に語っていただける空間になっています。
参考記事
Social Good Circleが誕生した背景や、Social Good Circleの詳しい説明は下記の記事をご覧ください。


【ご提案】職場でSocial Good Circle開催のお手伝い
Social Good Circleは「否定せず、助言せず、解決もしない」語らいの場として開催しています。このコンセプトは一見すると、対人援助の場面では否定的な意見を浴びるかもしれません。なぜなら「モヤモヤ=困っていること」と捉えることで、「職員が困っていることを、上司及び同僚同士で解決しなければならない」との思考に対して、真逆の発想でSocial Good Circleを開催しているからです。
僕は決して、「解決しなければならない」とする思考や行動を否定したいわけではありません。必要に応じて解決を優先する場合もあると理解しています。しかし解決を優先するがあまり、モヤモヤを抱えている職員が本当に困っていることを語れるかは疑問が残るところです。このように考えるには過去の記憶が起因しています。
僕は約6年間、病院のソーシャルワーカーとして働いていました。普段の業務とは別に個々のスキル向上やいわゆる「困難事例」に対する次の一手を模索するため、定期的に事例検討会をソーシャルワーカー同士で開催していました。いま振り返ると事例検討会は、ギリシャのコロッセオを彷彿とさせる思いで参加していたように思えます。要するに「戦いに挑む」という表現がわかりやすいでしょうか。雰囲気も戦々恐々としており、ミスを説明しようもんなら鬼の首を取ったような勢いで「なぜそうしたのか?」と問い詰められる。最初は初任者として「学ばせていただく」という気持ちで挑んでいましたが、やがて心身ともに疲弊していく自分を自覚しました。心の余裕がなくなるので、ちょっとした指摘も癇に障りますし、自らも「指摘返し」のような、一種の報復に似たような振る舞いをしていたときもありました。このような状態になると事例検討会ではなく、ただの「足の引っ張りあい」です。その場では本音を誰も話さなくなっていました。恐怖と保身でしかないからです。
そんな過去を振り返って思うことがあります。
心理的安全性が担保された空間でなければ、人は自らのモヤモヤを決して語りはしない
自らが悩んでいること、困っていること、こんなことを話して大丈夫?と思っていることも、否定されないとわかっていると人は安全性を感じるとることができ、スーと話し始めます。「どうしたの?」「それで?」と急く必要はありません。Social Good Circleは「否定せず、助言せず」をモットーに開催しています。最初から参加者へ伝えることで、参加者同士の「ここは安全だ」という雰囲気が醸成されます。
Social Good Circleでは、実に多様性豊かなモヤモヤを訊くことができます。そしてモヤモヤの深堀りは、ソーシャルワーカーのアイデンティティを取り戻すことにもつながります。事例検討会のように追求型のスーパービジョンは、支援者が育たないどころかパワーレスに陥り、終いには退職することも考えられます。そうではなく、じっくりとその人のモヤモヤした語りを訊き、参加者同士でフィードバックすることで、モヤモヤを語った人は「私の話を訊いてくれた」「受け入れてくれた」とカタルシスを得ることになります。普段、支援者として支援対象者の話を聞くことには慣れていますが、自分の話を訊いてもらうことには慣れていない支援者が多いのが現状です。Social Good Circleはこのような「支援者の語りを訊く」ことを実践することで、先にも述べたとおり、ソーシャルワーカーのアイデンティティを取り戻す(エンパワーメントの促進)へつながります。
とはいえ、Social Good Circleを職場でやろうとすると、導入・進行・まとめといった一連の流れを、誰がどのようにするのか悩むことが考えられます。悩むうちにズルズルと流れていくことはよくある話です。そこでご提案です。
職場でSocial Good Circleが定着するまで、もしくは体験として実施する、お手伝いをさせていただきます
Social Good Circleを実際に運営している者が、ファシリテーターや運営面をサポートすることで、簡単にSocial Good Circleを職場で開催することができます。もちろん職場の目的や規模等に応じて、運営側が関わる濃淡を調整することも可能です。まずは下記の「お問い合わせフォーム」より、ご相談いただければと思います。
お問い合わせ確認後、運営側よりご連絡させていただきます。この「Social Good Circle」が支援者のエンパワーメントにつながること、そして多くの支援者が自分語りをすることで、一人で抱え込まなずパワーレスに陥らない環境を構築できることを願っています。長くなりましたが、ご興味がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
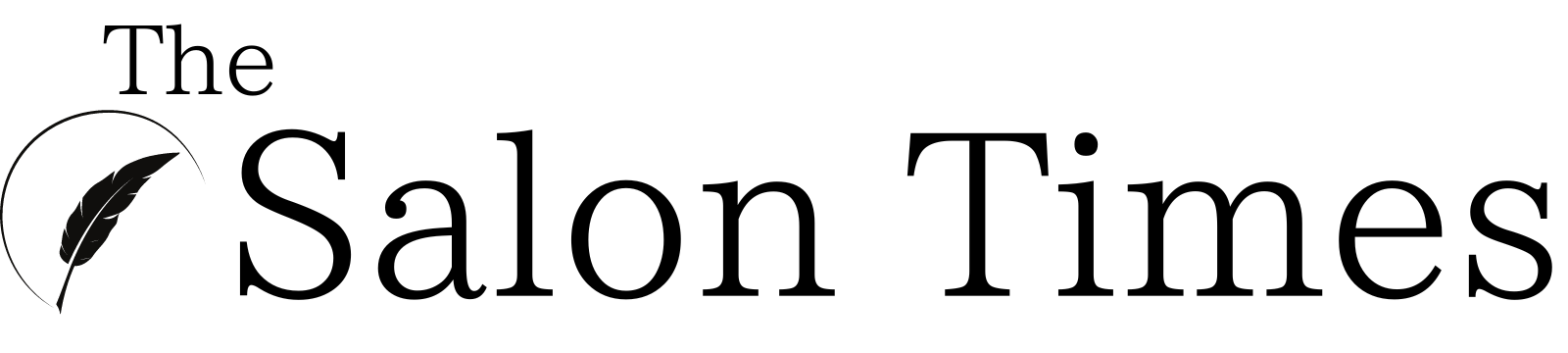
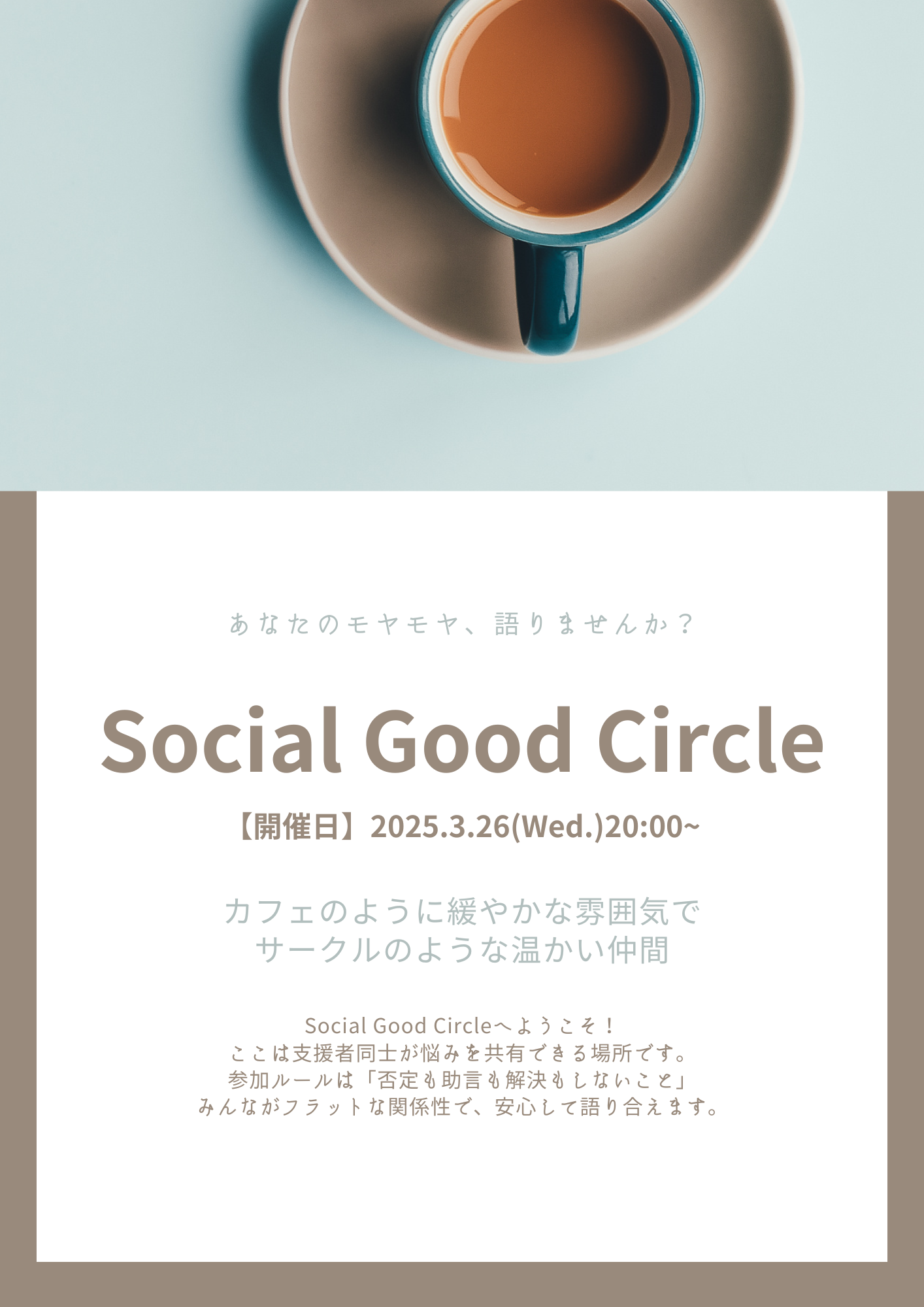

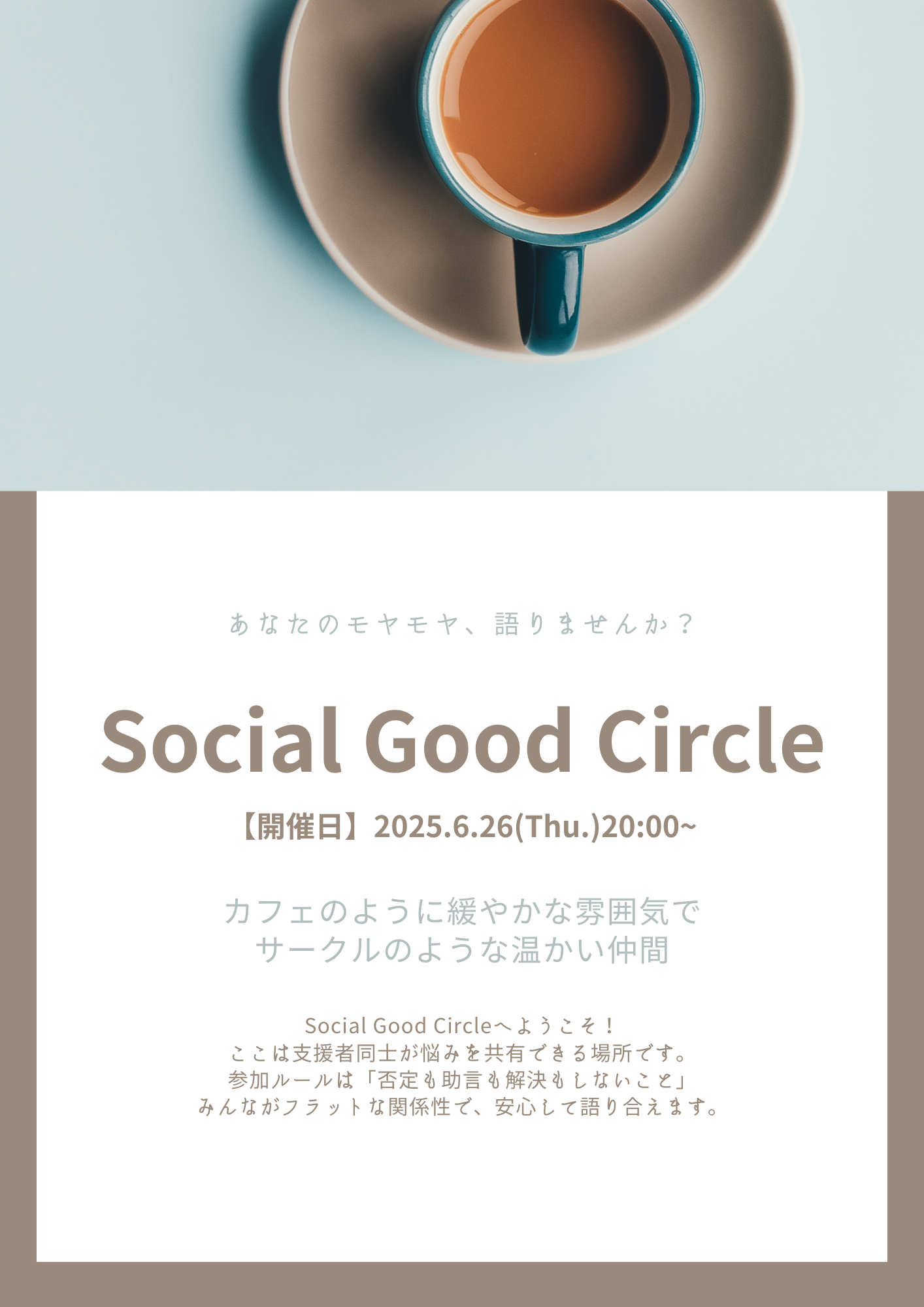

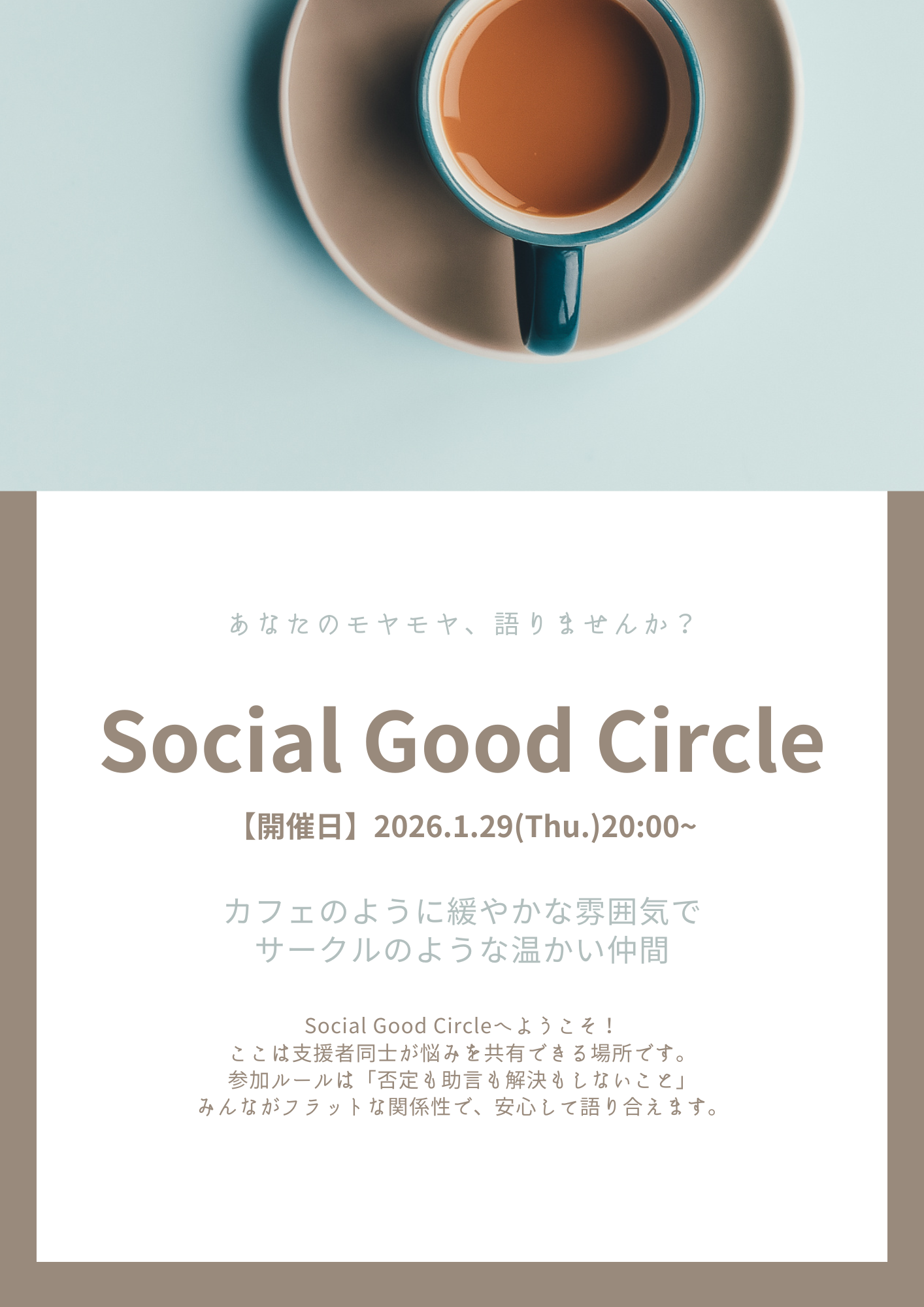

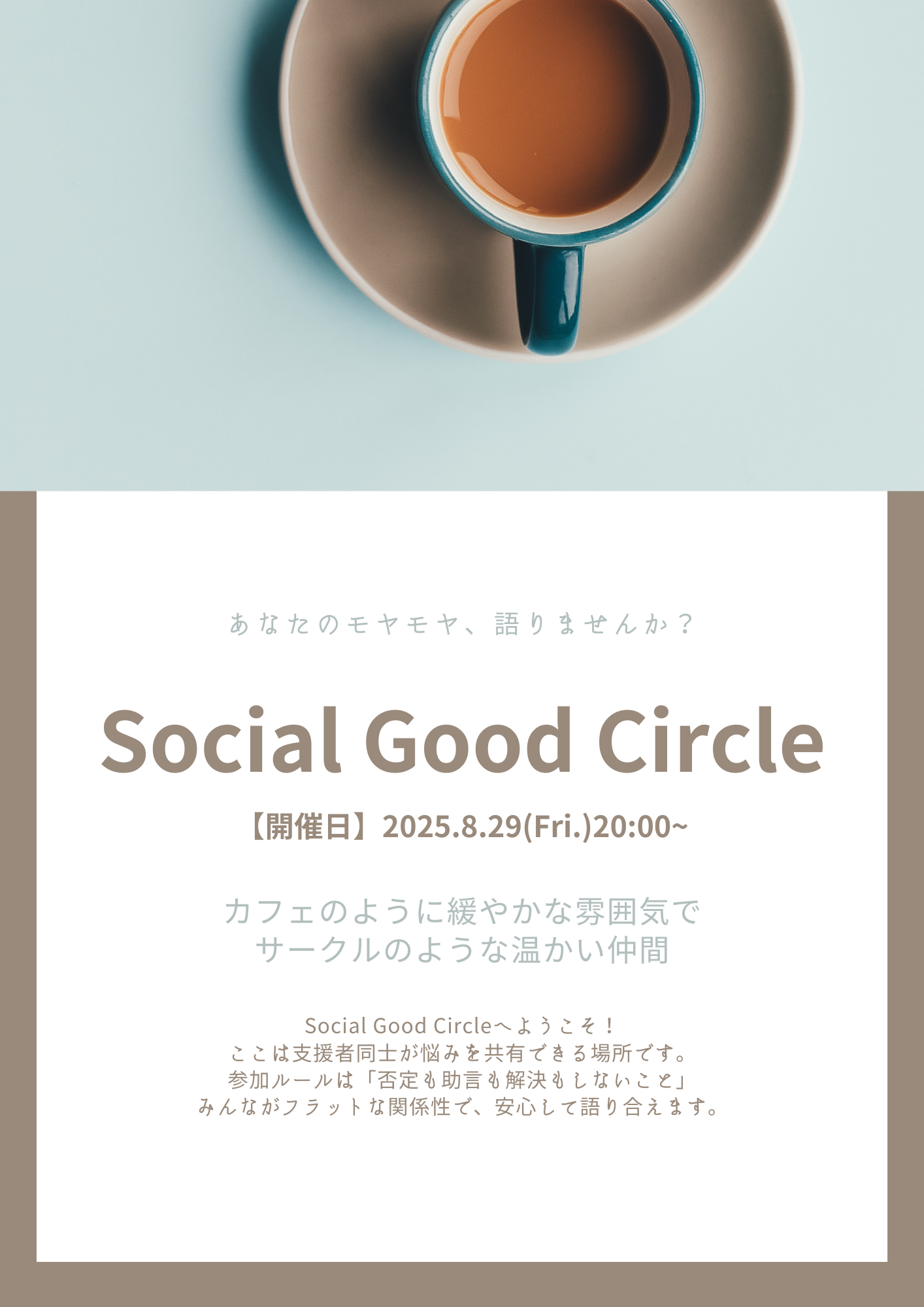


コメント