記事を読まれる前に「Social Good Circle」の申し込みをされたい方は、下記ボタンよりお願いします。
こんにちは。Social Good Circleの共同運営者をしている平畑です。
7月5・6日に島根県で開催された、「日本社会福祉士会全国大会」に参加してきました。そこで、東洋大学福祉社会デザイン学科教授の高山直樹先生より、『社会福祉士は真の権利擁護者になりえるか』というタイトルで基調講演を聴講しました。高山先生は、神奈川県意思決定支援専門アドバイザーとしても関わっておられ、2016年7月26日に起こった、津久井やまゆり園の事件についても意思決定支援の観点から言及しており、「支援者は、意思決定支援を支援者主導で進めるのではなく、本人は何を言いたいのか、何を望んでいるのか、何を想っているのかを様々な人や角度から聴くことと、その聴く環境を整え、意思を言える環境を創ることが支援となる」と、講演でおっしゃっていました。
また、日常の支援現場の中で「シカタガナイ」と言い、諦めてしまうことは、「何もしていない」ということと同義であり、支援対象者の力を奪ってしまうことにつながると、警鐘を鳴らしていました。「マンパワーが足りないから」「社会資源が足りないから」「障がいが重いから、高齢だから」「家族が言うから、決めているから」「法律や制度で決まっているから」。これら全てが、「シカタガナイ」として自らの職業倫理を放棄し、支援対象者の力を奪うことは、支援者の喜びを奪い、さらに組織の改革の機会も奪うことに繋がります。それは、人材確保の観点からもマイナスであり、事故を引き起こす可能性も高まります。そのような悪循環によって、虐待は生まれるとも言われています。
ではどうすればいいのか。高山先生は講演中、坂本いずみ・茨木尚子・竹端寛・二木泉・市川ヴィヴェカ『脱「いい子」のソーシャルワーク──反抑圧的な実践と理論』2021,現代書館を引用し説明されていました。
支援者自身が、自ら脅かす抑圧を「しょうがない」と受け入れたとき、支援を必要とする人に対し抑圧的なまなざしが向いてしまう。それが抑圧の再生産である。組織の機能不全や多数派の流れに疑問を持たない、もしくは異論の声をあげられない福祉職者が抑圧の一部となったとき、支援を必要とする人たちもまた、その抑圧構造に否応なくからめ取られていく。
福祉の世界には、様々な「抑圧」が蔓延し、「いい子」の支援者が結果的にその抑圧を後押ししてしまっている。そしてこの「抑圧」は、福祉現場に閉塞感をもたらし、ケアや支援の仕事を、つまらない・しんどい・希望のないものにしている。逆に言えば、「いい子」から脱し、抑圧に目をつぶらず、変えていく実践ができるようならば、支援現場の実践はもっと面白く、魅力的になる。これが本書の仮説である。
あきらめが権利侵害、そして虐待につながること。権利擁護(advocacy:アドボカシー)→「アラオカシー」から始まる。
坂本いずみ・茨木尚子・竹端寛・二木泉・市川ヴィヴェカ『脱「いい子」のソーシャルワーク──反抑圧的な実践と理論』2021,現代書館で取り上げている、「反抑圧的ソーシャルワーク(Anti-Oppressive Practice,通称AOP)は、支援者の「あきらめ」や「しょうがない」を『抑圧の内面化だ』と指摘しています。高山先生は、本来は社会的・構造的な抑圧や差別を、個人の能力不足や自己責任論というかたちにすり替えて、個人が我慢してそれでおしまい、としてしまうことは抑圧の温床であり、ひいては(無意識であっても)抑圧に加担していることになる、と指摘しています。
そのうえで、我慢やあきらめを超えて、「おかしいことはおかしい」と声をあげ、同じ考えを持つ仲間とつながり、支援現場や支援組織を変えていくことは可能である、とも私たち支援者に対して、エールを贈られていました。
僕は支援者として、いつもモヤモヤしていることを、高山先生の講演によって「そうだよな」と思わず膝を打ちました。現在の福祉構造は、サービスメニューは豊富になるものの、それを支援対象者へ当てはめてている、「マクドナルド化」が蔓延しています。「個別化」とよく耳にする反面、福祉の実態は「セットメニューが主語で、そのメニューを”支援者が”選んでいる」という、個別化とは程遠い場面が散見されます。
マニュアルに基づいた支援方法を身に着けてしまうと、そのマニュアルでは対応できない人に対して支援をする力量を育てる機会を奪うことにもなってしまう。例えば、介護保険の要介護認定や、障害者の要支援認定に基づいて、その枠内で制度利用をすることを前提に支援計画が策定されていくことに疑問を持たない、むしろそういった支援に親和性が高い支援者を育成していることに益々拍車がかかっているように思われる。(P115)
2年ごとに改定される診療報酬、3年ごとに改定される介護と障害福祉報酬。改定があるたび、必死に報酬内容を読解していく。これら報酬が私たちの生活に直結しているため、もちろん内容を理解し滞りなく混乱なく事務を行うことは必要なことですが、そこに支援対象者像が見えてこないことにモヤモヤします。「母体の報酬が下がった」「新たな加算が追加された」「ICTの導入、BCPの作成」などなど。踏襲された仕事をただただこなしていくこと、管理していく日課主義にモヤモヤします。
本来私たち支援者は、支援対象者の生活を豊かにしたり、その対象者と共に生活を支えていく、変化させていくことが仕事なのではないでしょうか。まさに「人間が人間を支えていく」ために、職業的価値や倫理を基盤として、知識・技術を提供していく。高山先生は、計画やモニタリングの過程に「本人が参画しているか?」と問うていました。それは、本人を中心に据えるのではなく、意思決定支援を中心に支援者や関係者の中に本人も入っていることが重要とおっしゃっていました。
さらに印象深かったのが、「本人が連れて来たい人を連れてくる」ということ。担当者会議やケア会議は、せいぜい親族が入る程度の印象ですが、「本人が連れて来たい人を呼ぶ」となれば、例えば、民生委員や自治会長に留まらず、友人・知人、同級生、飲み友達など多岐にわたっても良いとうことです。そういう風に「本人の意思を支援に参画する」ことで、本人が安心して本音で語れる環境づくりが進み、真の意思決定支援へとつながるのではないかと考えます。
「抑圧の内面化」は誰にだって潜んでいると思います。「”しょうがない”と思うな!」というのが、そもそも難しい。だからこそ、支援者同士での語り合いはとても大切なのではないでしょうか。
そして、その問題意識をともにする組織内、もしくは他組織に所属する仲間つまり、横のつながりを見つけ、集まり、語り合い、発信する。もちろん実際的な改革(意識改革や待遇改善)を組織内外で起こしていくことは素晴らしいが、私たちそれぞれの試行錯誤や悲喜こもごもの物語が、全く同じではないけれども、どこか似ている生きづらさを抱える者同士の間で語り合われ、共有財産として蓄積されていく。そして社会に向かって表明されていく。そのプロセス自体が癒しであり、エンパワメント(力づけ)として非常に効果性の高いAOPのアプローチになる。(P99)
Social Good Circleにも通じる文章だと思いました。急に社会変革へとつながることは難しいかもしれないが、目の前の仕事に対して、社会の構造に対して、支援者の倫理や社会的役割に対して、モヤモヤしていることを語り合うことは、それだけでカタルシスが生まれ、結果的に支援者のエンパワメントになるのだと。支援者自身が抑圧されている現状が、「あきやめ」や「しょうがない」という『抑圧の内面化』へと生成されることは、支援者が権利侵害を被っているいることと同じではないかと感じます。支援者の権利(またはアイデンティティ)を取り戻すためにも、「どこか似ている生きづらさを抱える者同士の間で語り合われ、共有財産として蓄積されていく。そして社会に向かって表明されていく」ことが、いま支援者に必要とされていることなのかもしれません。
「しんどい! けどしょうがない」より「しんどい! からどうしよう」、そのほうがなんだか明るい、よりよい、人が幸せな社会に近づいていく力の使い方のような気がしないだろうか?(P102)
「しんどい!」と思うことが誰にでもあり得ること。「しんどいと思うな!」と言われることで、ますますパワーレスになる。そうではなく、「しんどい!」と思ったときに、語り合える仲間の存在が、「しんどい! からどうしよう」という展開へと進んでいくと思っています。そのためには、Social Good Circleのような、「否定も助言もしない、ただただ語り合う」場所があると、なんだか明るい、よりよい、人が幸せな社会に近づいていく力の使い方のような気がしてきます。
Social Good Circleでは「物語で訊く」実践の場でもあると思っています。「助言も否定もしない」ため、診断分類には属しません。語ってもらったモヤモヤを訊いてどう感じたか、そして「そのモヤモヤをもっと知りたい、教えてほしい、さらに似たような体験や感じたことを語らせてもらいたい」という、語り合いの中での相互作用が生まれる場でもあります。そのような考えを見事に言語化されている文章を引用します。
例えば、ある人のストレスが高まり、眠れない状態が続くなかで、幻覚や妄想に苦しむようになったとしよう。あるいは自殺企図が生じ、暴力的な言動をするようになった。これを診断分類という「構造」に当てはめて、統合失調症や気分障害などの症状として確定させようとする。これは「あらかじめ『フレーム』によって対象と『時間』を区切り、限定された因果関係で理解しようとする手法」である。だが、幻覚や妄想を抱く人が、なぜそうなったのかは、そのフレーム=構造=診断分類からはわからない。会社・学校・家庭でハラスメントを受けた、失業や親しい人との別離に遭遇した、トラウマ的な体験や症状に苦しんでいる、強いストレスに長期間さらされ続けてきた、社会の同調圧力になじめず自己を抑圧している……といった、一人ひとりが抱える「複雑に相互作用し、非線形性によって支配される複雑な現象」を、そのものとして理解しないと、他ならぬその人が「いま・ここ」で抱える、生きる苦悩の最大化としての精神疾患の全体像(=構造化のダイナミクス)を捉えることができない。(P130)
これは、職場でも支援者同士でも思い当たることが多いのではないでしょうか。職場でミスをした際、上司から叱責される場合、「できない人」という烙印を押されることは、一種の診断分類という「構造」に当てはめられているのだと考えます。そうではなく、「なぜそのミスが生じたのか」「そのミスはいつから発生しそうだったのか」「その人の働く環境はどのような状態なのか」など、「複雑に相互作用し、非線形性によって支配される複雑な現象」から理解することが、真の意味で、対象者を理解することにつながるのだと思います。
Social Good Circleでは、語りたい場面から語ってもらうことで、訊いている側は、「複雑に相互作用し、非線形性によって支配される複雑な現象」に戸惑うときがあります。しかし支援現場でも同じようなことが起こっていると思います。「Aのことを話していると思ったら、急にDまで飛んで、今度はZまで行ったかと思ったら、Aに戻って来た」という、支援対象者の語りはこういうことの繰り返しが多いと感じています。Social Good Circleでもまとまりのない語りはあるものの、訊く側が、おずおずと語りの深化へと誘うようなお尋ねをしたり、自らも語ることで、メインで語って下さっている人が、「私がモヤモヤしていることって、こういうことなのかもしれない」とカタルシスを得る体験へと繋がっていきます。参加者全員で、他ならぬその人が「いま・ここ」で抱える、生きる苦悩の最大化を図ることで、語る人のモヤモヤを全員で受け止め、共振している場面も見られるのが、Social Good Circleの特徴の一つでもあります。
高山先生は、「弱さの力」についても言及されていました。「弱さとは、強さが弱体化したものではない。弱さとは、強さに向かうための一つのプロセスでもない。弱さとしての意味があり、価値がある」と。『「弱さ」のもつ可能性と底力』については、浦賀べてるの家『べてるの家の「非」援助論』2002,医学書院で下記のように述べています。『「強いこと」「正しいこと」に支配された価値のなかで、「人間とは弱いものなのだ」という事実に向き合い、そのなかで「弱さ」のもつ可能性と底力を用いた生き方を選択する。そんな暮らしの文化を育て上げてきたのだと思う。』(P194)
モヤモヤを語り合うことは、その人の「弱さ」を表出することでもあります。しかし弱さは簡単には出てきません。通常、人は弱さを隠そうします。それは『「強いこと」「正しいこと」に支配された価値』が関係しているとも、高山先生が説明されていました。Social Good Circleでも序盤から「弱さ」を全開に表出する人はあまりおらず、おずおずと語り始める方が大勢を占めます。それでも「弱さ」を語ってしまう理由としては、「助言も否定もしない」ことがわかっており、心理的安全性が担保されていると理解されているからだと感じています。そして、「訊いてくれる」ことも作用しているのではないかと。感じたことをフィードバックする展開が、「訊いてくれる」というある意味、承認欲求を満たすことにつながっていると思います。そのような満たされる体験が、支援者同士のエンパワメントを促進するのではないかと捉えています。
支援者も振り回されて疲れ果てているなら、支援者も自身の無力さを認め、支援の行き詰まりを解決するために、本人や家族、他の支援者に助けを求めるしかない。(P137)
僕は支援現場において、「弱さ」を開示する場面が多々あります。わからないことを一緒に悩んだり、「難しい」と苦悩したり、「今は何かできることが見つからない」と嘆いたり…。しかしこの「弱さの共同作業」が、僕という支援者も支援対象者の本人も、エンパワメントされる機会に恵まれるときがあります。「弱さ」を開示することは、「弱さを認めること」にも繋がります。他者の「弱さ」を見ることで、自らの「弱さ」を認め、表出へと向かえばと考えています。Social Good Circleでも同じことが言え、「弱さの共同作業」が展開されています。これは、決して傷の舐め合いではなく、「弱さ」を認め合うからこそ、対等な関係性へと変化し、共に困難な状況を乗り越えるステップになるのだと思っています。
今回は、日本社会社会福祉士会全国大会(島根大会)で聴講した、高山直樹先生の講演内容と、引用箇所は坂本いずみ・茨木尚子・竹端寛・二木泉・市川ヴィヴェカ『脱「いい子」のソーシャルワーク──反抑圧的な実践と理論』2021,現代書館から引用し、Social Good Circleにおける相互作用を考えてみました。興味のある方は、ご自身の「弱さ」を安全な空間で語ってみませんか?下記に申込方法を記載していますので、そちらのフォームからお願いします。皆さんのご参加をお待ちしています。
Social Good Circle 開催詳細
Social Good Circleには多くの方が参加しやすいように、オンライン開催としています。仕事から帰ってきてひと段落した時間帯にすることで、ゆったりと語り合えるようにしています。以下、開催詳細をご覧ください。
開催日
- 2025年7月25日(金)20:00〜21:30
参加方法
- オンライン(zoom使用)
申し込み後に招待URLを送らせていただきます。
参加費
- 無料
気軽に参加できるよう参加費はいただいておりませんが、今後対面で開催することも検討しています。
その際は参加費を頂戴する場合がありますのでご容赦ください。
申込方法
下記の「申し込みフォーム」と書かれているボタンをクリックすると、申し込むフォームへ移動します。
必要項目を入力していただき、送信後、開催に関するメールが届きます。
申込手順
まずは申し込みフォームの入力をお願いします。ご不明な点があれば、お問い合わせからご連絡ください。
Social Good Circleとは
Social Good Circleは「支援者のモヤモヤをダイアローグする場」としています。よって、参加者同士の上下関係もなく、全てがフラットです。日々の実践や人間関係など、モヤモヤしていることを語っていただき、聞く側は助言も否定もせず、ただただ訊くことに徹します。
もちろん訊いた後に、自らのモヤモヤを語っていただくことも大歓迎です。「今更こんなことは職場で話せない」や「誰か私のモヤモヤを訊いてほしい」など、Social Good Circleにおいては気楽に語っていただける空間になっています。
参考記事
Social Good Circleが誕生した背景や、Social Good Circleの詳しい説明は下記の記事をご覧ください。

【ご提案】職場でSocial Good Circle開催のお手伝い
Social Good Circleは「否定せず、助言せず、解決もしない」語らいの場として開催しています。このコンセプトは一見すると、対人援助の場面では否定的な意見を浴びるかもしれません。なぜなら「モヤモヤ=困っていること」と捉えることで、「職員が困っていることを、上司及び同僚同士で解決しなければならない」との思考に対して、真逆の発想でSocial Good Circleを開催しているからです。
僕は決して、「解決しなければならない」とする思考や行動を否定したいわけではありません。必要に応じて解決を優先する場合もあると理解しています。しかし解決を優先するがあまり、モヤモヤを抱えている職員が本当に困っていることを語れるかは疑問が残るところです。このように考えるには過去の記憶が起因しています。
僕は約6年間、病院のソーシャルワーカーとして働いていました。普段の業務とは別に個々のスキル向上やいわゆる「困難事例」に対する次の一手を模索するため、定期的に事例検討会をソーシャルワーカー同士で開催していました。いま振り返ると事例検討会は、ギリシャのコロッセオを彷彿とさせる思いで参加していたように思えます。要するに「戦いに挑む」という表現がわかりやすいでしょうか。雰囲気も戦々恐々としており、ミスを説明しようもんなら鬼の首を取ったような勢いで「なぜそうしたのか?」と問い詰められる。最初は初任者として「学ばせていただく」という気持ちで挑んでいましたが、やがて心身ともに疲弊していく自分を自覚しました。心の余裕がなくなるので、ちょっとした指摘も癇に障りますし、自らも「指摘返し」のような、一種の報復に似たような振る舞いをしていたときもありました。このような状態になると事例検討会ではなく、ただの「足の引っ張りあい」です。その場では本音を誰も話さなくなっていました。恐怖と保身でしかないからです。
そんな過去を振り返って思うことがあります。
心理的安全性が担保された空間でなければ、人は自らのモヤモヤを決して語りはしない
自らが悩んでいること、困っていること、こんなことを話して大丈夫?と思っていることも、否定されないとわかっていると人は安全性を感じるとることができ、スーと話し始めます。「どうしたの?」「それで?」と急く必要はありません。Social Good Circleは「否定せず、助言せず」をモットーに開催しています。最初から参加者へ伝えることで、参加者同士の「ここは安全だ」という雰囲気が醸成されます。
Social Good Circleでは、実に多様性豊かなモヤモヤを訊くことができます。そしてモヤモヤの深堀りは、ソーシャルワーカーのアイデンティティを取り戻すことにもつながります。事例検討会のように追求型のスーパービジョンは、支援者が育たないどころかパワーレスに陥り、終いには退職することも考えられます。そうではなく、じっくりとその人のモヤモヤした語りを訊き、参加者同士でフィードバックすることで、モヤモヤを語った人は「私の話を訊いてくれた」「受け入れてくれた」とカタルシスを得ることになります。普段、支援者として支援対象者の話を聞くことには慣れていますが、自分の話を訊いてもらうことには慣れていない支援者が多いのが現状です。Social Good Circleはこのような「支援者の語りを訊く」ことを実践することで、先にも述べたとおり、ソーシャルワーカーのアイデンティティを取り戻す(エンパワーメントの促進)へつながります。
とはいえ、Social Good Circleを職場でやろうとすると、導入・進行・まとめといった一連の流れを、誰がどのようにするのか悩むことが考えられます。悩むうちにズルズルと流れていくことはよくある話です。そこでご提案です。
職場でSocial Good Circleが定着するまで、もしくは体験として実施する、お手伝いをさせていただきます
Social Good Circleを実際に運営している者が、ファシリテーターや運営面をサポートすることで、簡単にSocial Good Circleを職場で開催することができます。もちろん職場の目的や規模等に応じて、運営側が関わる濃淡を調整することも可能です。まずは下記の「お問い合わせフォーム」より、ご相談いただければと思います。
お問い合わせ確認後、運営側よりご連絡させていただきます。この「Social Good Circle」が支援者のエンパワーメントにつながること、そして多くの支援者が自分語りをすることで、一人で抱え込まなずパワーレスに陥らない環境を構築できることを願っています。長くなりましたが、ご興味がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
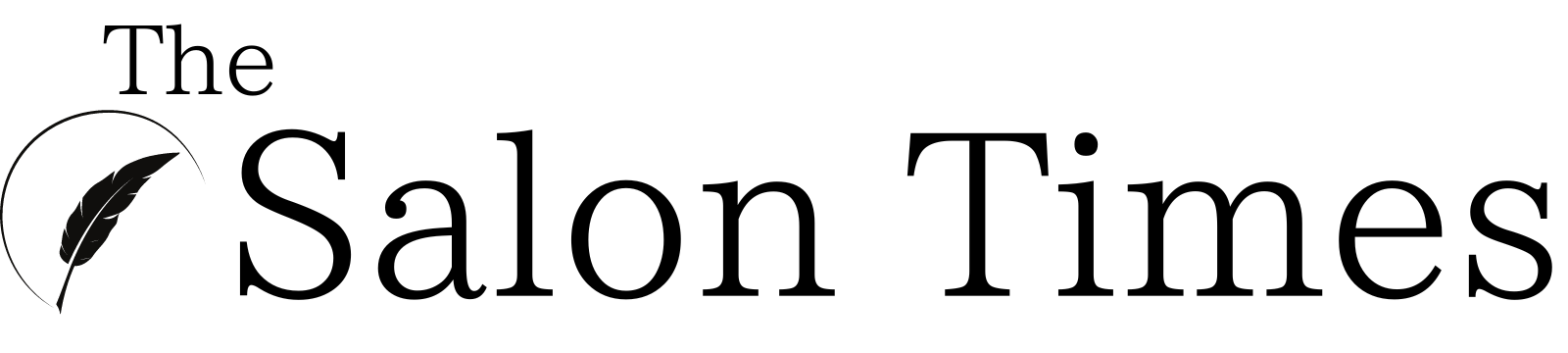
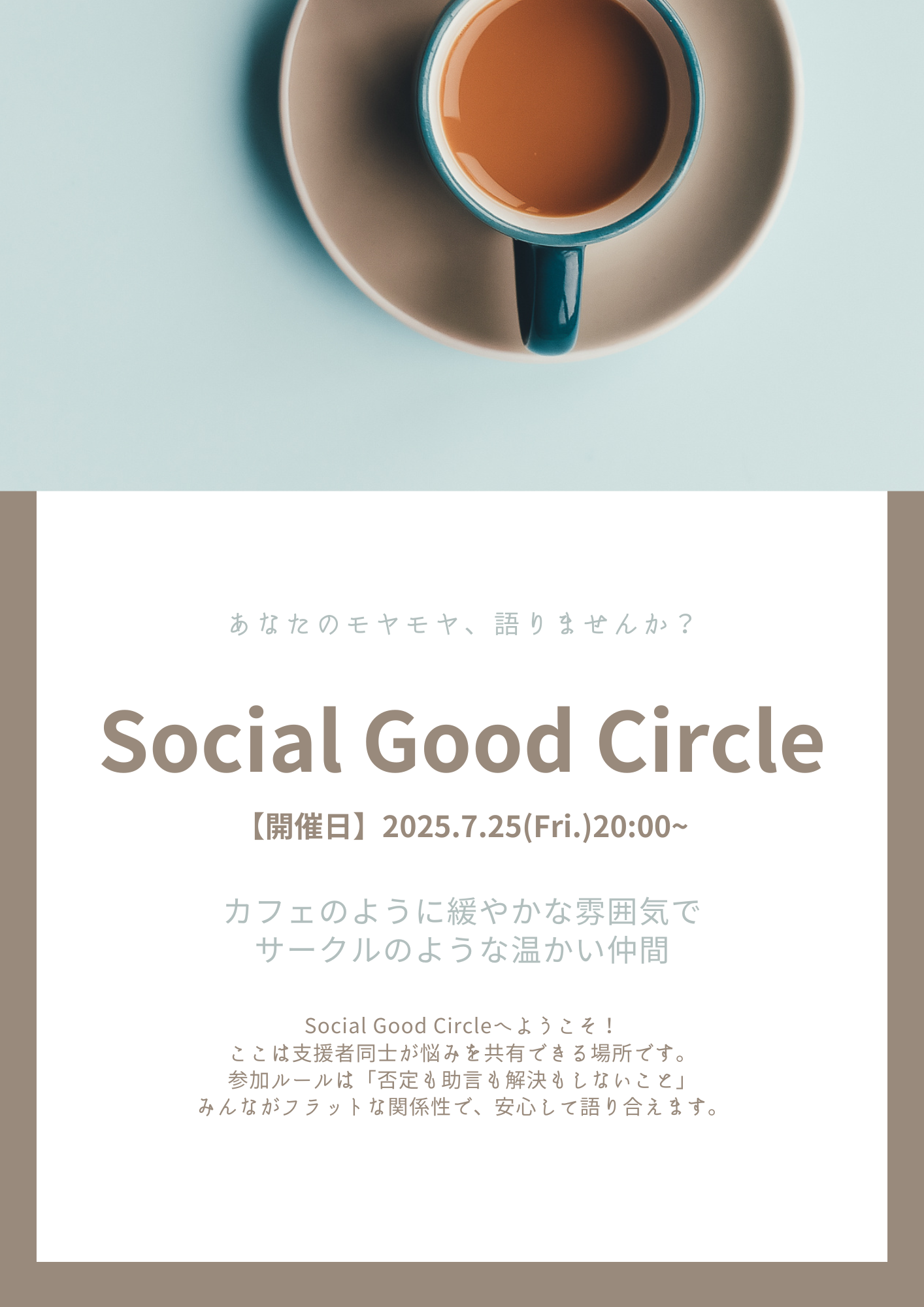

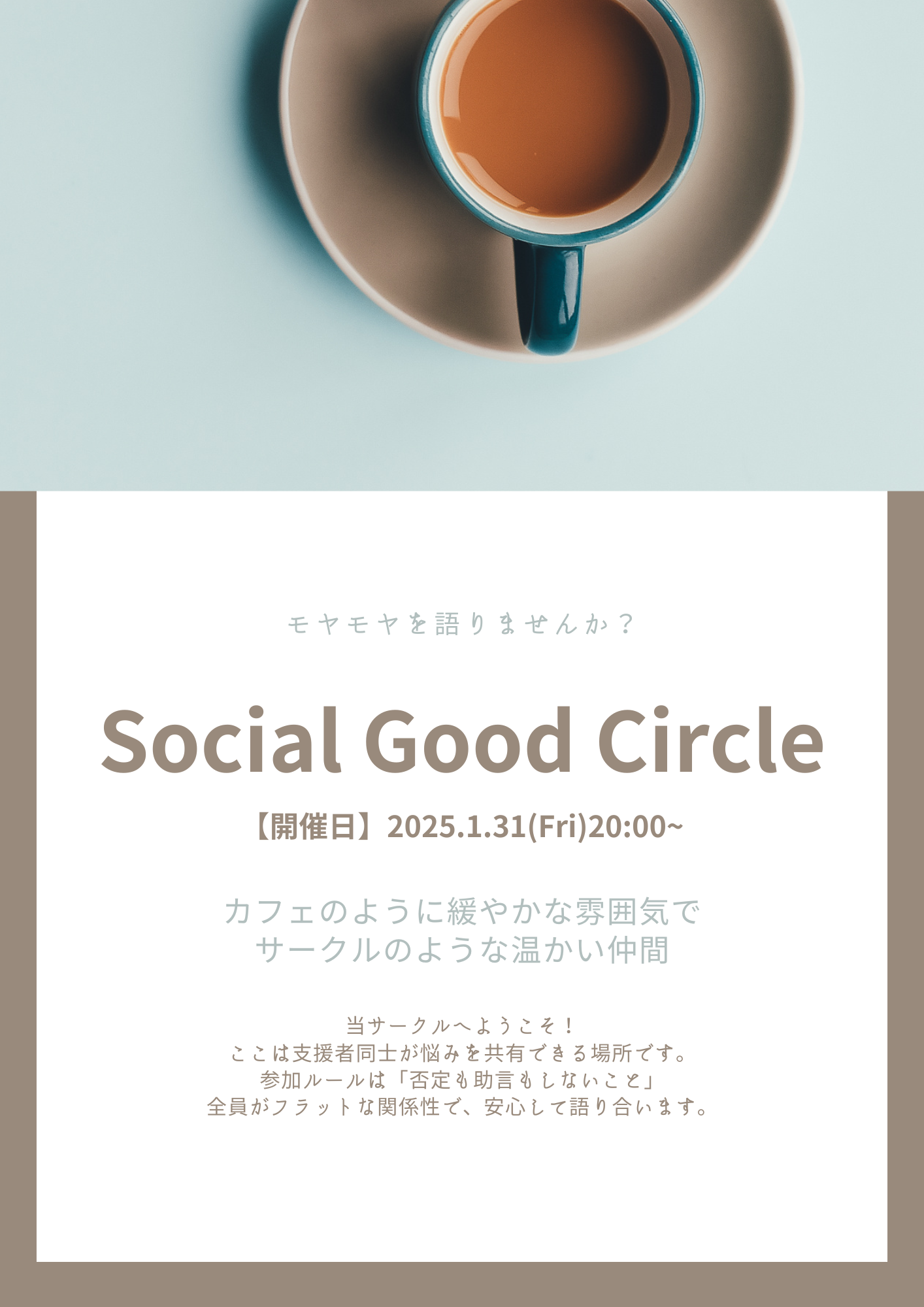

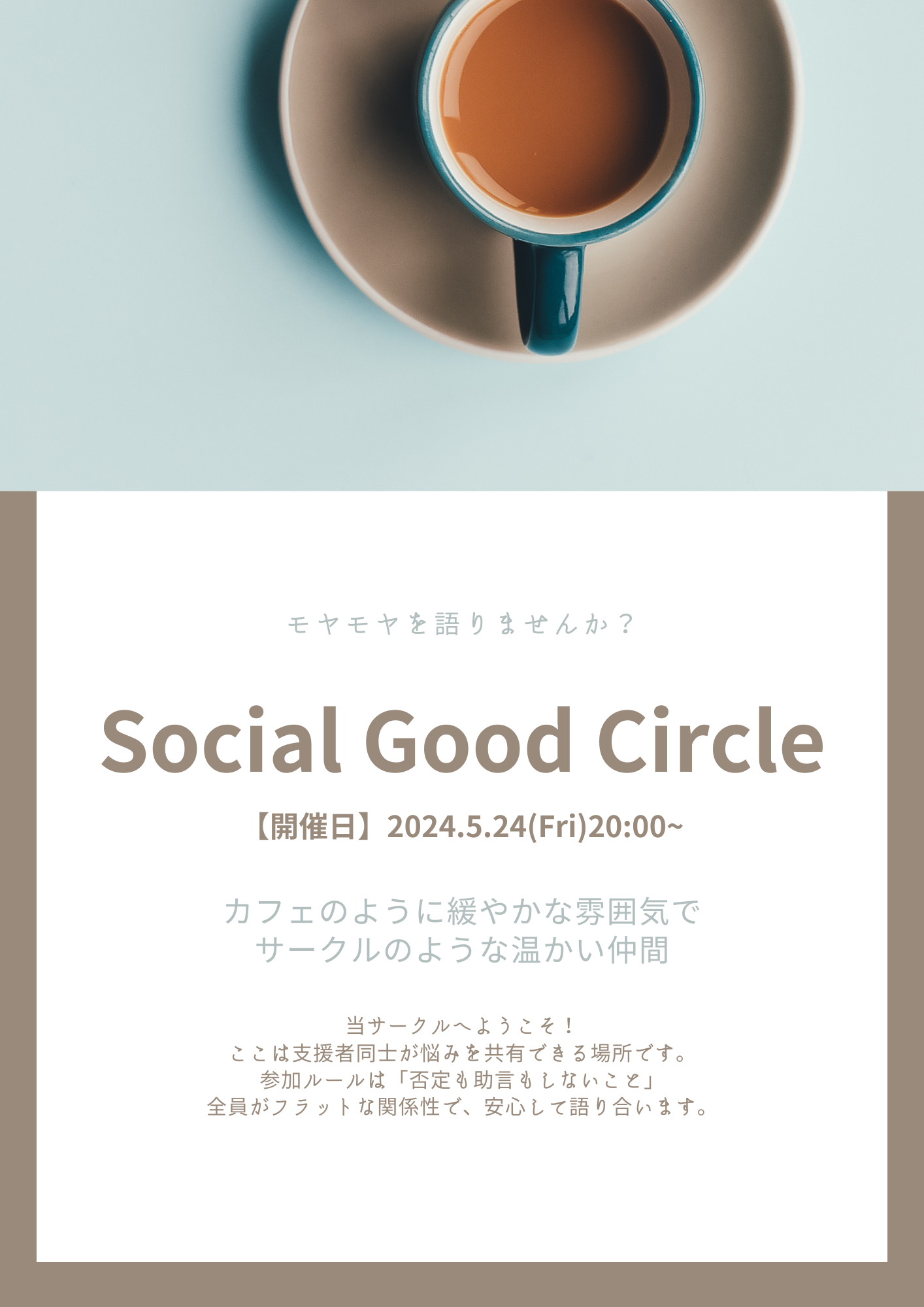



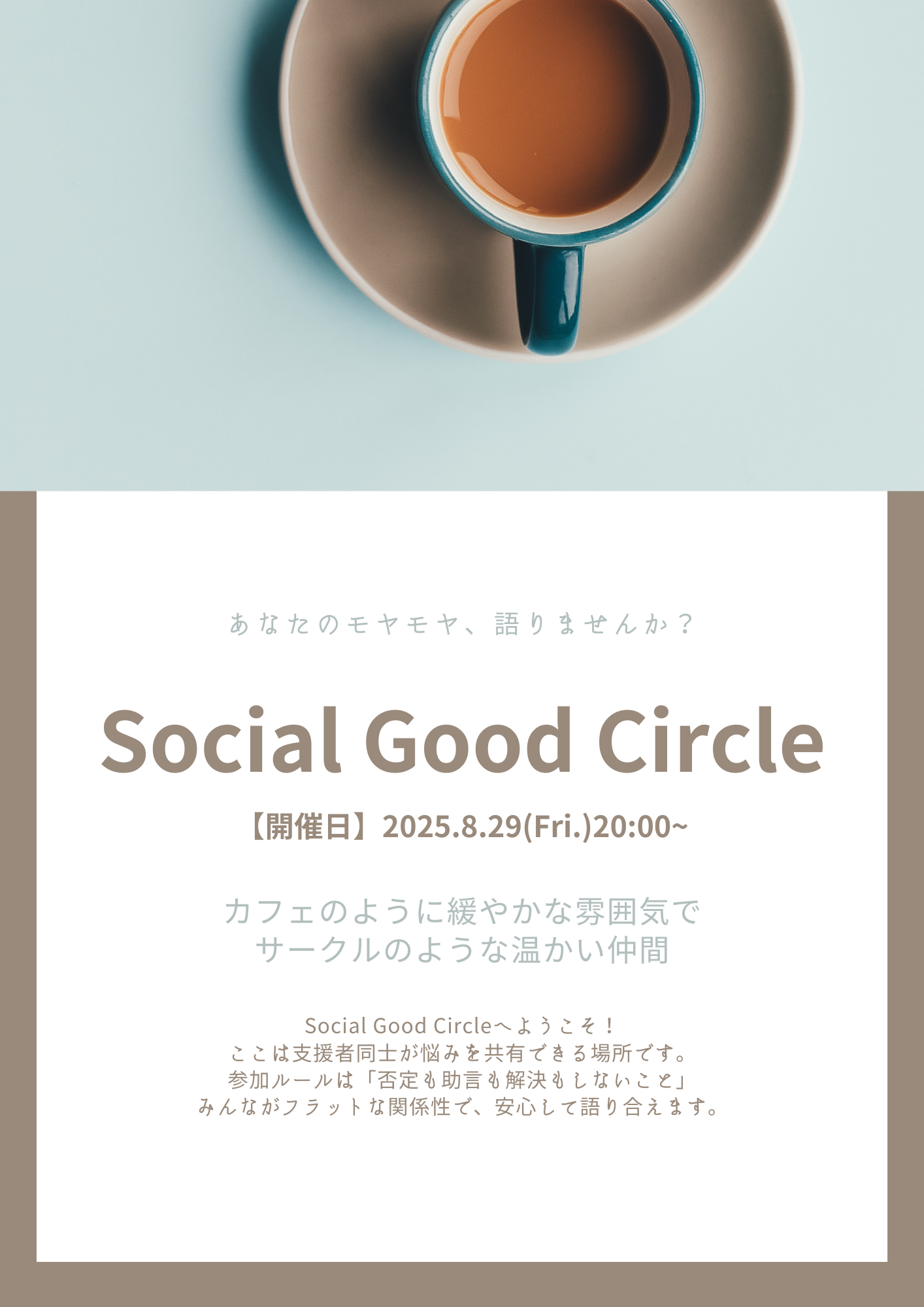
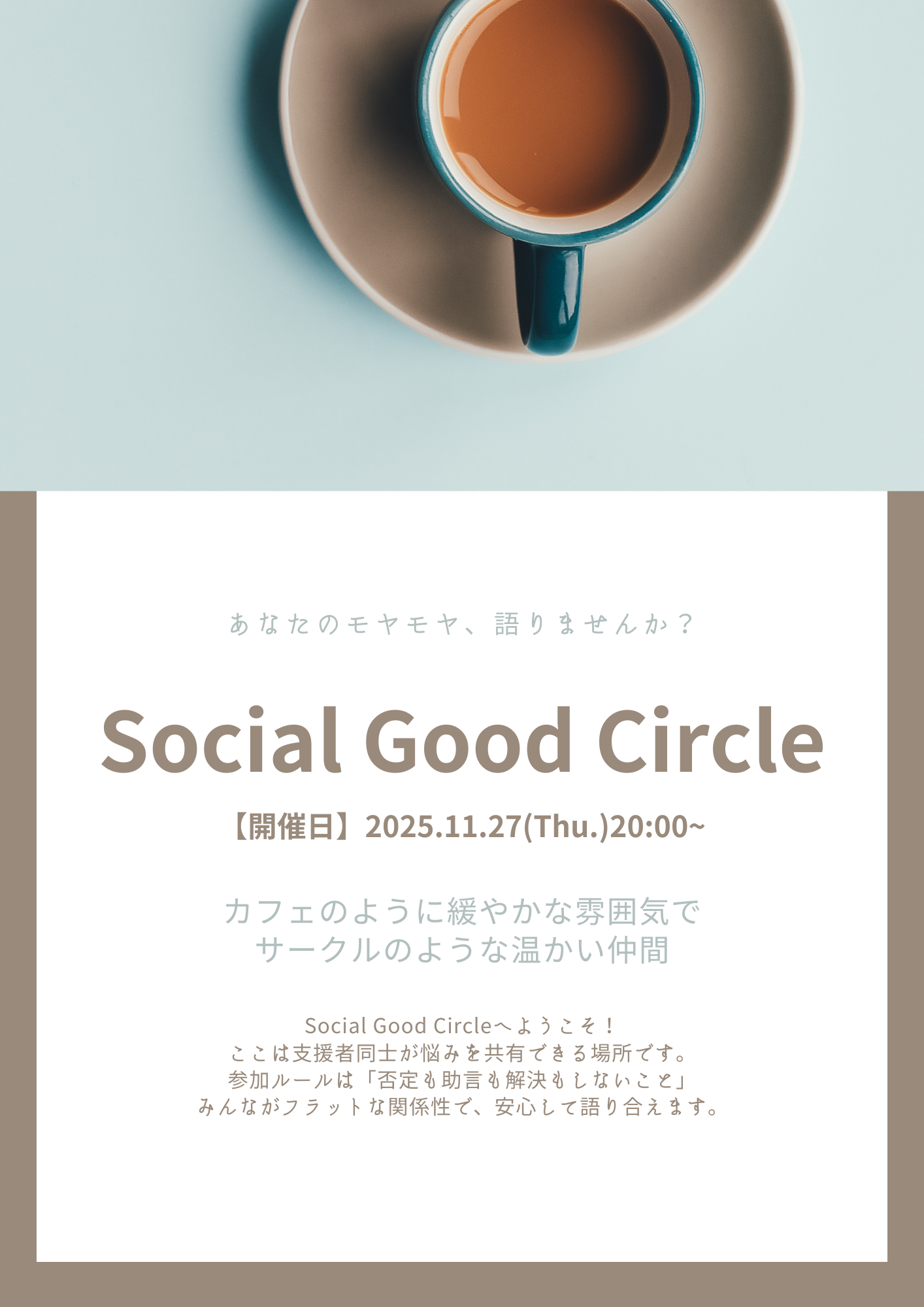
コメント