記事を読まれる前に「Social Good Circle」の申し込みをされたい方は、下記ボタンよりお願いします。
こんにちは。Social Good Circleの共同運営者をしている平畑です。
3月に開催してから早3ヶ月。桜が咲こうとしていた時期から、本格的な梅雨の季節となりました。季節の移り変わりは早いもので、と同時に僕自身、毎日の忙しさに流されていることに対して、「もう少しゆっくり時間の経過を楽しみたい」と思うこの頃です。
Social Good Circleを休止していた3ヶ月、改めて「対話」について思考を巡らせていました。福祉分野における支援者間の対話にとどまらず、会社、学校、地域、社会、という幅広い分野での対話の可能性について。そして、対話をする前後における、個人の変容や他者及び環境(社会含む)との相互作用など。
昨年一気読みした、兵庫県立大学(当時は山梨学院大学)・竹端寛さんの『枠組み外しの旅ー「個性化」が変える福祉社会』青灯社(2012)を、最近再読しました。竹端さん(普段は”先生”だが、Social Good Circleではフラットな関係性を尊重しているため、”さん”呼称とする)とは、3年前から開催している、『”フツーの人”のまちづくりの学校in長崎(現:無理しない地域づくりの学校in長崎)』で知り合い、当初受講生だった僕は、自らを主語にした問い直しを繰り返し行うことで「マイプラン」を作成し、今まで当たり前と思っていた、規範的な枠組みを外す体験をしました。『”フツーの人”のまちづくりの学校in長崎』については、【「“フツーの人”のまちづくりの学校」で作成したマイプラン】間違いなく人生のターニングポイントになった、で講座の概要や僕のマイプランの作成経緯がわかるように書いているので、興味がある方はご一読されてみてください。
改めて、本書を読み進めていると、「Social Good Circleで実践している『対話』とはそもそも何なのか?」ということを、問い直すきっかけを与えてくれました。本書では重要なキーワードが2つ出てきます。「枠組み外し」と「学びの渦」です。竹端さんは冒頭で以下のように説明しています。
「枠組み外し」とは何か。簡単に言えば、私達が「当たり前の前提」としている、「変えられない」と思い込んでいる「常識」「暗黙の前提」そのものを疑うことである。(P17)
「学びの渦」とは何か。それは、渦の主体となる個人が、自らが囚われている枠組みの限界に気づき、その枠組みを外す学習プロセスに身を置くことから始まる。(P17)
Social Good Circleで対話実践していると、固定化された価値基準によってモヤモヤしたり、にっちもさっちも行かない状態で苦しんでいる方がおられます。その価値基準は、「あなたの感想ですよね」みたいな個人要因ではなくて、今まで過ごされてきた環境から影響を受けていることが大きいと思います。さらに言えば、「〇〇ならそうすべき」とか「〇〇だからしょうがない」といった、私達が「当たり前の前提」としている規範的な社会構造によって、固定化された価値基準が形成されているのかもしれない、と考えています。「枠組み外し」とは、私たち自身の「常識」「暗黙の前提」そのものを疑うことであると同時に、このような「枠組み外し」がSocial Good Circleでは、ナチュラルに行われている場面があります。
それはなぜか?まさに「学びの渦」が作用しているからだと本書を読んで気づいたところです。Social Good Circleでは、『否定も助言もせず、ただただ発言者の語りを最後まで訊く』ことをルールとしています。よって、発言者は「こんなことを言って場違いだと思われたらどうしよう」と怯えることなく思考を巡らせながら、湧き上がる言葉をポツリポツリと表出してくれます。一方、心理的なバイアスがかかっていると、たとえ言葉が湧き上がってきたとしても、表出されるまでには至らず、まるで固形物を丸呑みするかのように消化不良となり、その場から遠ざかっていくことが想定されます。Social Good Circleの中で「学びの渦」が発生するのは、心理的に安心した状態だからこそ、自らが囚われている枠組みの限界に気づけるのだと思います。語りの多様性を尊重している場では、「語っていいんだ」と思うことに加え、「変わってもいい」という、変容可能性を促す作用も見受けられるのではないかと思っています。
時にSocial Good Circleでは、「自らの役割」にモヤモヤしている方の語りを訊くことがあります。「”ソーシャルワーカーとして”〇〇という個別課題をどう捉えたらいいか」という具合に。語りをじっくり訊いていくと、「ソーシャルワーカーとしての仕事は面白いのだが、どこか不全感というかモヤモヤを抱えている」ということがわかりました。
そのためにはまず、あるエクリチュールや循環性に「支配されていることを自覚すること」が求められる。「タケバタヒロシ」が「大学准教授」の役割期待を無自覚に引き受け、自らの言葉遣いや話し方、考え方や振る舞いをどれほど限定づけているか。その「限定」が、自己決定なのではなく、社会常識や通念に「支配されていること」にもとづく不自由な状態であると「自覚すること」。その上で、その支配構造=悪循環構造を「反省的に主題化」できればよいのである。(P45)
上記の「役割期待」については、ソーシャルワーカーでも看護師でも弁護士でも、様々な職業に変換できます。つい「ソーシャルワーカーとは」などと、自らの職業倫理に照らし合わせた規範的行動をとりがちですが、僕たちはそれが、社会常識や通念に「支配されていること」に気づく必要があるのではないでしょうか。Social Good Circleでは、職業としての”私”は一旦横に置き、『個人としての”私”としてどう思うか』を問い直す場面があります。そうすることで、自由な語りが生まれ、社会常識や通念に「支配されていること」にもとづく不自由な状態であると「自覚すること」にもつながります。そのような経過を辿ることで、自らの役割期待からの呪縛性から解き放たれるのではないかと思っています。
Social Good Circleでは、主に相談援助を生業としている方々が多く参加していますが、活動されている分野は多岐にわたります。高齢・障害・児童・困窮・地域・司法・教育など、さまざまです。同じ社会福祉士でも分野も社会的立立場が違うと、価値観や倫理観も微妙に違ってくる。それは必然的なことかもしれません。そのような方々とフラットな関係性で語り合うSocial Good Circleでは、「メッセージの交換」によって「動的な調和」が構築されていきます。そのことを竹端さんは以下のように述べています。
医師とソーシャルワーカー、行政職員と民生委員など、職種や社会的立場、そして個性も人格も違う人々が、もともと「同じ何かを共有」している、というのは幻想である。でも、そこに集う人びとが「相互に学習過程を作動させて」、相手の「投げかけるメッセージ」を「心から受け止めて自己を変革」をしようとするならば、その「メッセージの交換」がその場に集った人びと全体の中で相互作用化するならば、そこにはお互いの「相違を原動力として進む」「動的な調和」としての「和」が作動する。(P59)
Social Good Circleに通じる一節だなと感じました。対話を始める前から、「同じ何かを共有」している、という幻想は抱いていません。むしろ『モヤモヤという唯一無二の語りを通して、「私はどう思うか」という、「心から受け止めて自己を変革」しようとする、自己変容作用が巻き起こることにワクワクしたりもします。少しの変容を認め、少しずつ語り合うことで、「メッセージの交換」がその場に集った人びと全体の中で相互作用化することは、Social Good Circleの中で何度も見てきた光景です。その中で、やはり大事なことは、違いを認め合うコミュニケーションだと思います。自分とは違う考え方や立場の意見を訊くことによって、「なぜそう考えるのか」「その語りの背景は何か」と他者の語りに対する興味関心は、お互いの「相違を原動力として進む」「動的な調和」としての「和」が作動することにつながるのではないかと考えます。
そのようにSocial Good Circleを捉えると、Social Good Circleは「自ら開くコミュニケーションの場」だと言えるのかもしれません。ソーシャルワーカーのような対人援助職は、『他者の語りを訊く』ことが支援の出発点だと、僕は捉えています。他者の語りを訊かない支援はあり得ないし成立しない。しかしながら、その『訊く』における、権力と情報の非対称性が強い場面は、支援現場では往々に存在します。「支援する人・支援される人」の構図は、『他者の語りを訊く』ことを「卑屈な役割関係」へと貶めてしまいます。
権力や情報の非対称性が強い学校や福祉現場では、教育者や福祉専門家が提唱する「あるべき姿」像(=自らの作り上げた神話)という「正しさ」を、「賦活させ、協力に支配していく」現実が見受けられる。先生や専門家の言うことだから「正しい」、と。(P73)
僕自身、恥を曝け出すと、上記の一節に身に覚えがありますし、それは自覚しているときもあれば無自覚のときもある。後に実践を振り返ったときや、コミュニケーション不足が露呈した際に、無自覚的な権力や情報の非対称性に恐れを抱く時があります。さらに、「平畑さんの言うとおりで大丈夫」「よかった、受け入れてくれた」という、卑屈な役割関係が、対象者の語りを減少させ、支援者としてのアセスメントができなくなるといった、支援体制の根幹を揺るがす事態に陥るといっても過言ではないかもしれません。
Social Good Circleでも同じことが言えると思います。一方的に指導したり否定したり(Social Good Circleでそんなことはないが)することで、「自ら開くコミュニケーション」には発展しません。そこには関係性が大切になってくることが、竹端さんの一節で理解できます。
まずは支援する・教える側が、一方的な「注意・宣言・恫喝」という「反ー対話」をやめ、「対話」に入らなければならない。そうしないと、「反ー対話」を変えられない現実と受け止めて諦めている、支援される・教わる側の「宿命論的な認識」そのものを変えることは出来ない。「対話」とは、それほど根幹的であり、支援する側・教わる側への変容を迫るものなのである。(P75)
それは、相手とのコミュニケーション方法を「自分は知らない」し、その結果として相手の「本音」を「知らない」という「無知」を素直に認めることからスタートする。(P80)
「あの人(対象者)はなぜ、私の質問に答えてくれないんだ」「聞いてもいつも曖昧な返答しか返ってこない」「毎回、あなたの言うとおりで大丈夫、と言われる」など、僕自身心当たりがある言葉ですが、これらは「反ー対話」を変えられない現実と受け止めて諦めている、支援される・教わる側の「宿命論的な認識」が一つの要因だと思います。要は「諦め」。「どうせ言っても仕方ない」といった、「宿命的な認識」を持たれていると、いつまで経っても対話は成立しません。さらに、その要因を作り出しているのは、紛れもなく支援者自身だということを、肝に銘じなければならない。話を遮ったり、すぐ要約したり、説得したり、聞かなかったり。それらの「反ー対話」的姿勢は、対象者の心に深く刻み込まれ、それらが「困難事例」として挙げられ、右往左往する羽目になる場合もあるということを、自戒を込めて書きたいと思います。大切なのは、相手の「本音」を「知らない」という「無知」を素直に認めることからスタートすることではないでしょうか。Social Good Circleでは、意見を押し付ける場ではないので、「他者のことはわからない」ということを前提に対話が進められていきます。よって、「知らないことは知らない」と言ってもいい雰囲気が醸し出されており、それが結果的に「反ー対話」を参加者全員で締め出している格好になっているわけです。
長年、ソーシャルワークをしていると、つい支援の「正解」を見出そうとしてしまいます。「対象者にとって何が一番よかったのだろうか」とモヤモヤすることは今でもありますが、そもそも支援現場において「正解」とは何なのでしょうか。竹端さんは「正解」の対置として「成解」という概念を述べています。
「正解」と対置した「成解」概念とは、ローカルな文脈という「空間限定的」で、かつあるタイミングでのみ適合するという「時間限定的」な制約を持つ概念である。そして、「当面成立可能で受容可能」で、その現場を変えうる力を持つ「解」としての「成解」こそが、福祉現場にも求められる知そのものである。(P154)
ソーシャルワークの現場では、ジレンマがありとあらゆるところで発生しています。発生する理由として、教科書的な知識及び規範的な価値基準と、曖昧で変則的に変化する対象者のニーズとでは凸凹だらけで、綺麗に合わせようとするほうが、支援者として傲慢だと僕は感じているからです。対象者のニーズは空間でも時間でも変化することから、唯一無二の「正解」を持ち出したところで…という感じ。そのような変化があることに自覚的になり、「当面成立可能で受容可能」で、その現場を変えうる力を持つ「解」としての「成解」こそが、現場には求められているのだと思います。まずは「成り立たせること」、柔軟さを持つことが大切で、そのためには、『枠組みを外す』ことが求められます。このような柔軟な発想は、Social Good Circleの中で結構出てくる概念であり、「正解幻想」に縛られてないからこそできる対話の力なのかなと自負しています。
Social Good Circleでは、自由な対話を実践しています。「自分語りをしてもらたい」という願いを込めて、「あなた個人としてはどう思うか」と質問させてもらうときも。本書では、竹端さんがスイスの心理学者であるユング(1995)の一節を引用しています。
対話の中で、ついつい職業的価値に重きを置いて語りをされる方はいます。それはいたし方のないことだと思います。ただ他者の語りを訊いて、多様な思考に触れることで、自己変容できる機会は目の前にあるわけで。でも、自ら「蓋」をしてしまうことで、「そうは言ってもね…」というネガティブ思考のままでいるのは、ちょっと勿体無いような気がします。竹端さんは「個性化」について、下記のように効果を述べています。
あるシステム下において、自らと対象者、あるいは渦、を切り分けていたら、「新しい関係」も「新しい価値」も生まれない。「個性化」が利己主義や個人主義とは違う、というのは、僕とあなた、精神障害者と地域社会、などを切り分けず、「両者を、相互に依存し、影響し合う一つのシステムとして認識」する渦作りと、その渦の展開を指すからである。それは、個人の問題でもありながら、同時に「人間の集合的な使命を、よりよく、より完全に満たすこと」につながっている。(中略)何よりも先に、あなたや僕自身が、自らの個性化に取り組むことは、社会への働きかけを真っ当なものとし、「人間の集合的な使命を、よりよく、より完全に満たす」変化をもたらす「共生的価値創出」のために、必要不可欠な第一歩なのである。(P191)
対話の際、主語を「私」として語ることを促すことがありますが、それは個人主義に傾斜しているものではありません。「メッセージの交換」によって、他者のことを「知る」ことから始める。そうやって、僕とあなた、精神障害者と地域社会、などを切り分けず、「両者を、相互に依存し、影響し合う一つのシステムとして認識」する渦作りをすることによって、自分も他者も一緒に変容していくのだと思います。変容の過程は、最初からダイナミックな渦もあれば、小さかった渦が大きくなるより、連鎖反応的に発生し、さらに「人間の集合的な使命を、よりよく、より完全に満たす」変化をもたらすようなかたちで、やがて大きな渦へと変貌することだってあります。語りを訊きながら、自分の問題として受け止め、知ることで自ら変容していく。そういう姿を他者が眺めることで、その他者自身も自分のこととして受け止め始めると、「学びの渦」が発生するのだと思っています。
そう書いていると、「個性化」とは自分語りをするだけではなく、人との関係性にも関連していることがとてもわかります。
個性化が利己主義と違うのは、「かかわりの視点」を持った「関係的主体」として認識する点である。僕とあなた、する側とされる側、個人と社会の「両者を、相互に依存し、影響し合う一つのシステムとして認識」する点が、自他を切り分けて考える利己主義との最大の違いである。(P210)
Social Good Circleでも、参加者同士が「かかわりの視点」を持った「関係的主体」として認識することで、「今日はとてもいい話を訊けた」「皆さんからいただいた言葉を胸に、明日から変わっていこうと思う」など、「両者を、相互に依存し、影響し合う一つのシステムとして認識」しているからこそ、同時多発的に、大なり小なりの「渦」が発生しています。その渦に”うっかり”巻き込まれたり、自ら飛び込んだり、招き入れてもらったり。参加者全員がフラットな関係性だからこそ、相互に依存し、影響し合える土壌が初めから出来ているのだと思います。
ここまで書き進めてみて振り返ったことは、本書はSocial Good Circleにとっての「指南書」のようなものだな、と感じました。点と点だけでは決して「学びの渦」は発生しない。まずは他者との違い語りの中から丁寧に訊き、自分ごとのように受け止めて考える。そうすることで、自分自身が変容する姿を他者が眺めることで、相互に依存し、影響し合うように「学びの渦」が発生する。前提として、自分自身が問い直すこととは、「諦め」や宿命論といった、「どうせ」「しかたない」「無理だ」といった呪縛から解放することが求められます。
Social Good Circleでは、そのような「渦」が発生していますし、その「渦」が発生するプロセスを、本書において竹端さんは「渦的プロセス」と述べていました。このSocial Good Circleが、今後も支援者同士の拠り所として継続できるためには、フラットな関係性で「個性化」を表出できる雰囲気を続けていきたいと、決意を新たにしたところです。また、「学びの渦」が発生することで、Social Good Circleという枠から外れた先に、「社会変革」というかたちで、大きな渦にみんなで巻き込まれてもいいな、と思いつつ、6月のSocial Good Circleでお待ちしたいと思います。
Social Good Circle 開催詳細
Social Good Circleには多くの方が参加しやすいように、オンライン開催としています。仕事から帰ってきてひと段落した時間帯にすることで、ゆったりと語り合えるようにしています。以下、開催詳細をご覧ください。
開催日
- 2025年6月26日(木)20:00〜21:30
参加方法
- オンライン(zoom使用)
申し込み後に招待URLを送らせていただきます。
参加費
- 無料
気軽に参加できるよう参加費はいただいておりませんが、今後対面で開催することも検討しています。
その際は参加費を頂戴する場合がありますのでご容赦ください。
申込方法
下記の「申し込みフォーム」と書かれているボタンをクリックすると、申し込むフォームへ移動します。
必要項目を入力していただき、送信後、開催に関するメールが届きます。
申込手順
まずは申し込みフォームの入力をお願いします。ご不明な点があれば、お問い合わせからご連絡ください。
Social Good Circleとは
Social Good Circleは「支援者のモヤモヤをダイアローグする場」としています。よって、参加者同士の上下関係もなく、全てがフラットです。日々の実践や人間関係など、モヤモヤしていることを語っていただき、聞く側は助言も否定もせず、ただただ訊くことに徹します。
もちろん訊いた後に、自らのモヤモヤを語っていただくことも大歓迎です。「今更こんなことは職場で話せない」や「誰か私のモヤモヤを訊いてほしい」など、Social Good Circleにおいては気楽に語っていただける空間になっています。
参考記事
Social Good Circleが誕生した背景や、Social Good Circleの詳しい説明は下記の記事をご覧ください。

【ご提案】職場でSocial Good Circle開催のお手伝い
Social Good Circleは「否定せず、助言せず、解決もしない」語らいの場として開催しています。このコンセプトは一見すると、対人援助の場面では否定的な意見を浴びるかもしれません。なぜなら「モヤモヤ=困っていること」と捉えることで、「職員が困っていることを、上司及び同僚同士で解決しなければならない」との思考に対して、真逆の発想でSocial Good Circleを開催しているからです。
僕は決して、「解決しなければならない」とする思考や行動を否定したいわけではありません。必要に応じて解決を優先する場合もあると理解しています。しかし解決を優先するがあまり、モヤモヤを抱えている職員が本当に困っていることを語れるかは疑問が残るところです。このように考えるには過去の記憶が起因しています。
僕は約6年間、病院のソーシャルワーカーとして働いていました。普段の業務とは別に個々のスキル向上やいわゆる「困難事例」に対する次の一手を模索するため、定期的に事例検討会をソーシャルワーカー同士で開催していました。いま振り返ると事例検討会は、ギリシャのコロッセオを彷彿とさせる思いで参加していたように思えます。要するに「戦いに挑む」という表現がわかりやすいでしょうか。雰囲気も戦々恐々としており、ミスを説明しようもんなら鬼の首を取ったような勢いで「なぜそうしたのか?」と問い詰められる。最初は初任者として「学ばせていただく」という気持ちで挑んでいましたが、やがて心身ともに疲弊していく自分を自覚しました。心の余裕がなくなるので、ちょっとした指摘も癇に障りますし、自らも「指摘返し」のような、一種の報復に似たような振る舞いをしていたときもありました。このような状態になると事例検討会ではなく、ただの「足の引っ張りあい」です。その場では本音を誰も話さなくなっていました。恐怖と保身でしかないからです。
そんな過去を振り返って思うことがあります。
心理的安全性が担保された空間でなければ、人は自らのモヤモヤを決して語りはしない
自らが悩んでいること、困っていること、こんなことを話して大丈夫?と思っていることも、否定されないとわかっていると人は安全性を感じるとることができ、スーと話し始めます。「どうしたの?」「それで?」と急く必要はありません。Social Good Circleは「否定せず、助言せず」をモットーに開催しています。最初から参加者へ伝えることで、参加者同士の「ここは安全だ」という雰囲気が醸成されます。
Social Good Circleでは、実に多様性豊かなモヤモヤを訊くことができます。そしてモヤモヤの深堀りは、ソーシャルワーカーのアイデンティティを取り戻すことにもつながります。事例検討会のように追求型のスーパービジョンは、支援者が育たないどころかパワーレスに陥り、終いには退職することも考えられます。そうではなく、じっくりとその人のモヤモヤした語りを訊き、参加者同士でフィードバックすることで、モヤモヤを語った人は「私の話を訊いてくれた」「受け入れてくれた」とカタルシスを得ることになります。普段、支援者として支援対象者の話を聞くことには慣れていますが、自分の話を訊いてもらうことには慣れていない支援者が多いのが現状です。Social Good Circleはこのような「支援者の語りを訊く」ことを実践することで、先にも述べたとおり、ソーシャルワーカーのアイデンティティを取り戻す(エンパワーメントの促進)へつながります。
とはいえ、Social Good Circleを職場でやろうとすると、導入・進行・まとめといった一連の流れを、誰がどのようにするのか悩むことが考えられます。悩むうちにズルズルと流れていくことはよくある話です。そこでご提案です。
職場でSocial Good Circleが定着するまで、もしくは体験として実施する、お手伝いをさせていただきます
Social Good Circleを実際に運営している者が、ファシリテーターや運営面をサポートすることで、簡単にSocial Good Circleを職場で開催することができます。もちろん職場の目的や規模等に応じて、運営側が関わる濃淡を調整することも可能です。まずは下記の「お問い合わせフォーム」より、ご相談いただければと思います。
お問い合わせ確認後、運営側よりご連絡させていただきます。この「Social Good Circle」が支援者のエンパワーメントにつながること、そして多くの支援者が自分語りをすることで、一人で抱え込まなずパワーレスに陥らない環境を構築できることを願っています。長くなりましたが、ご興味がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
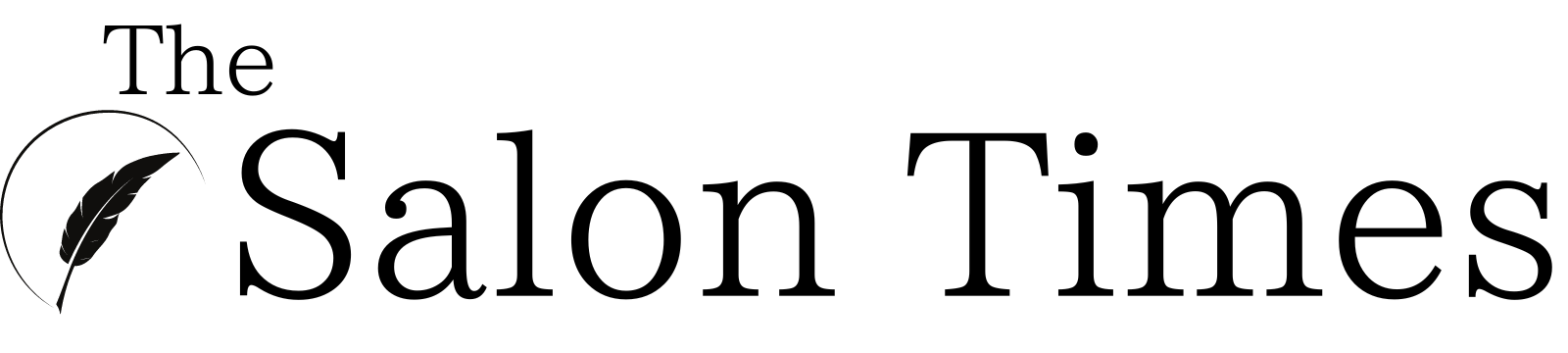
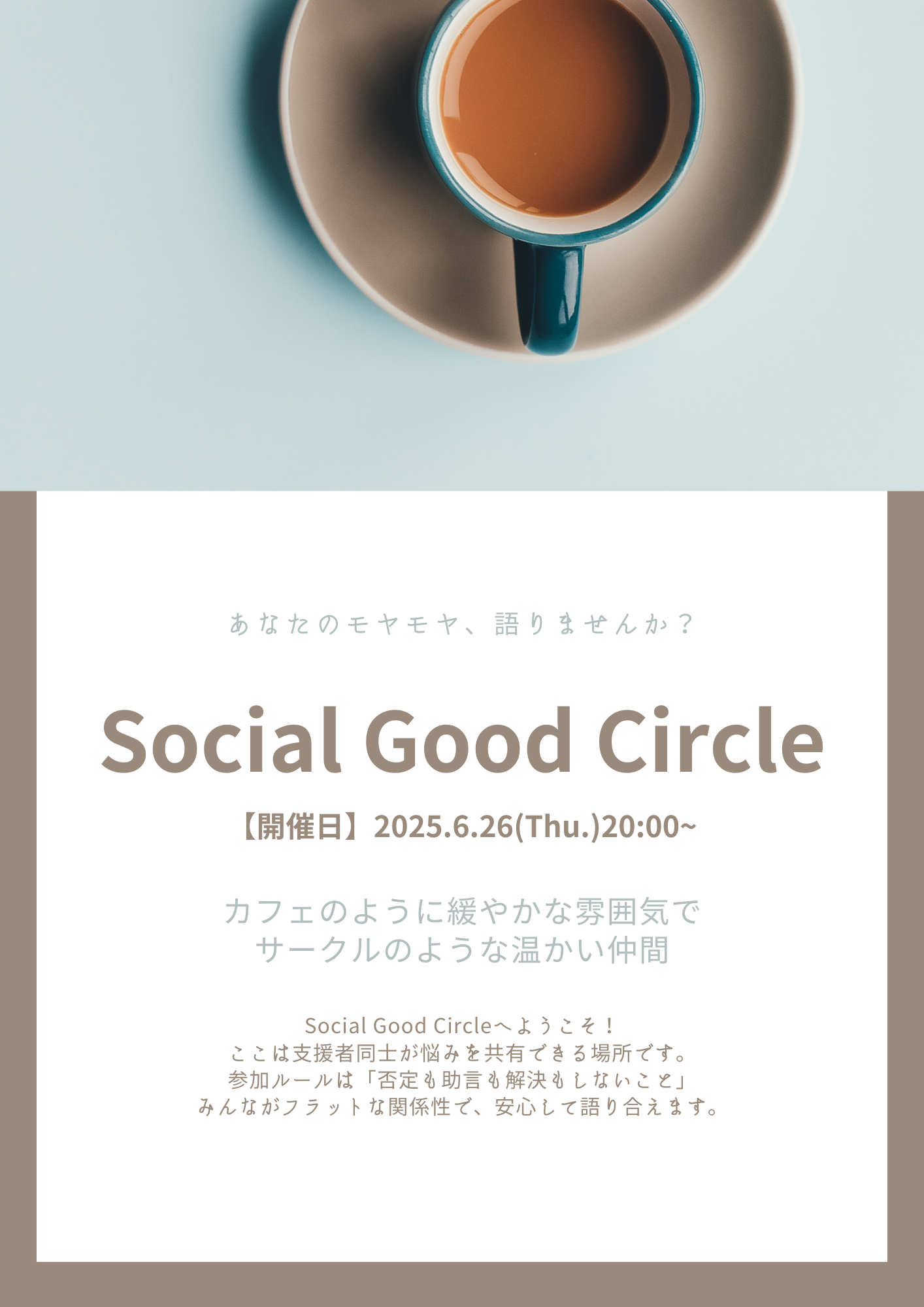



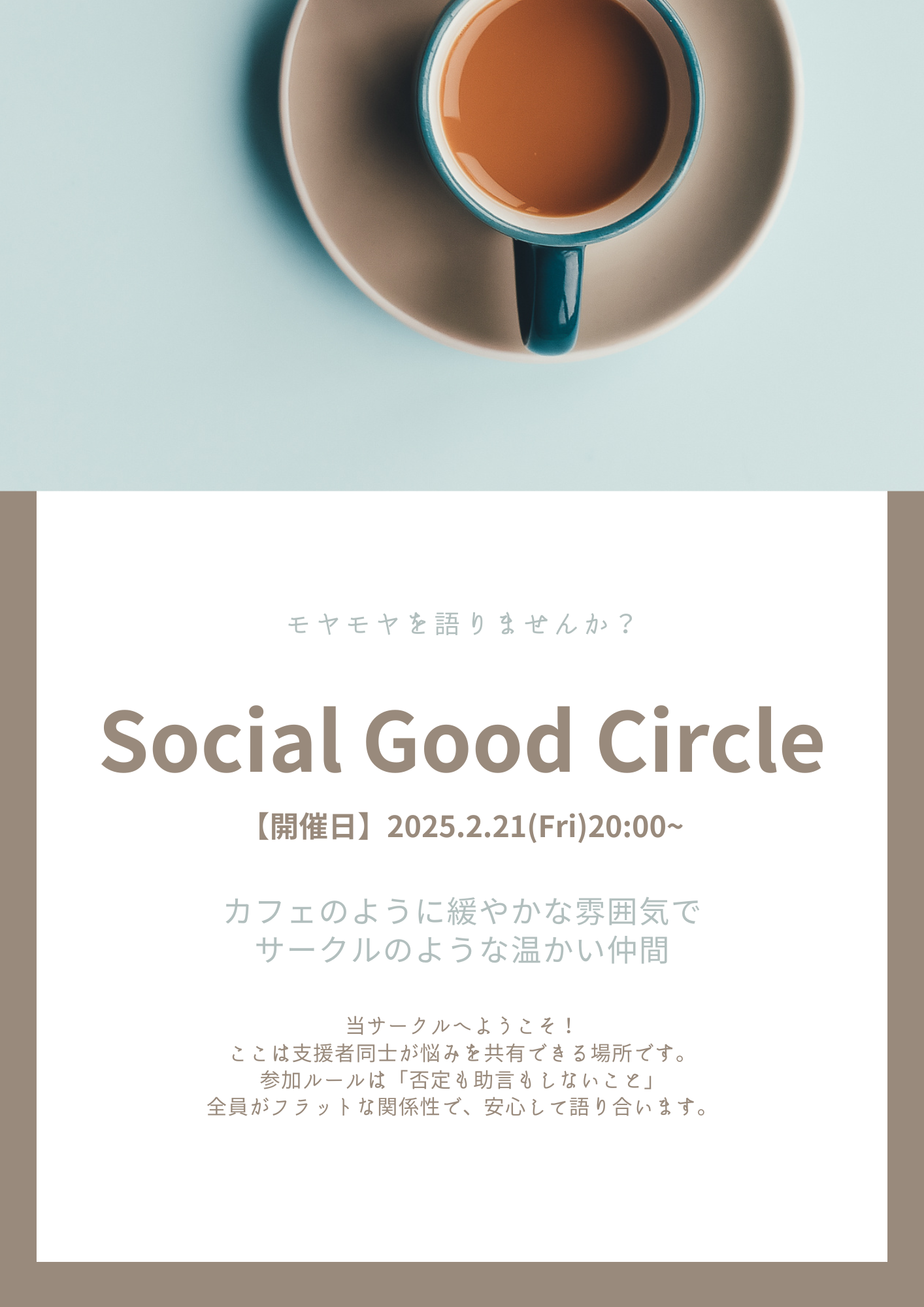

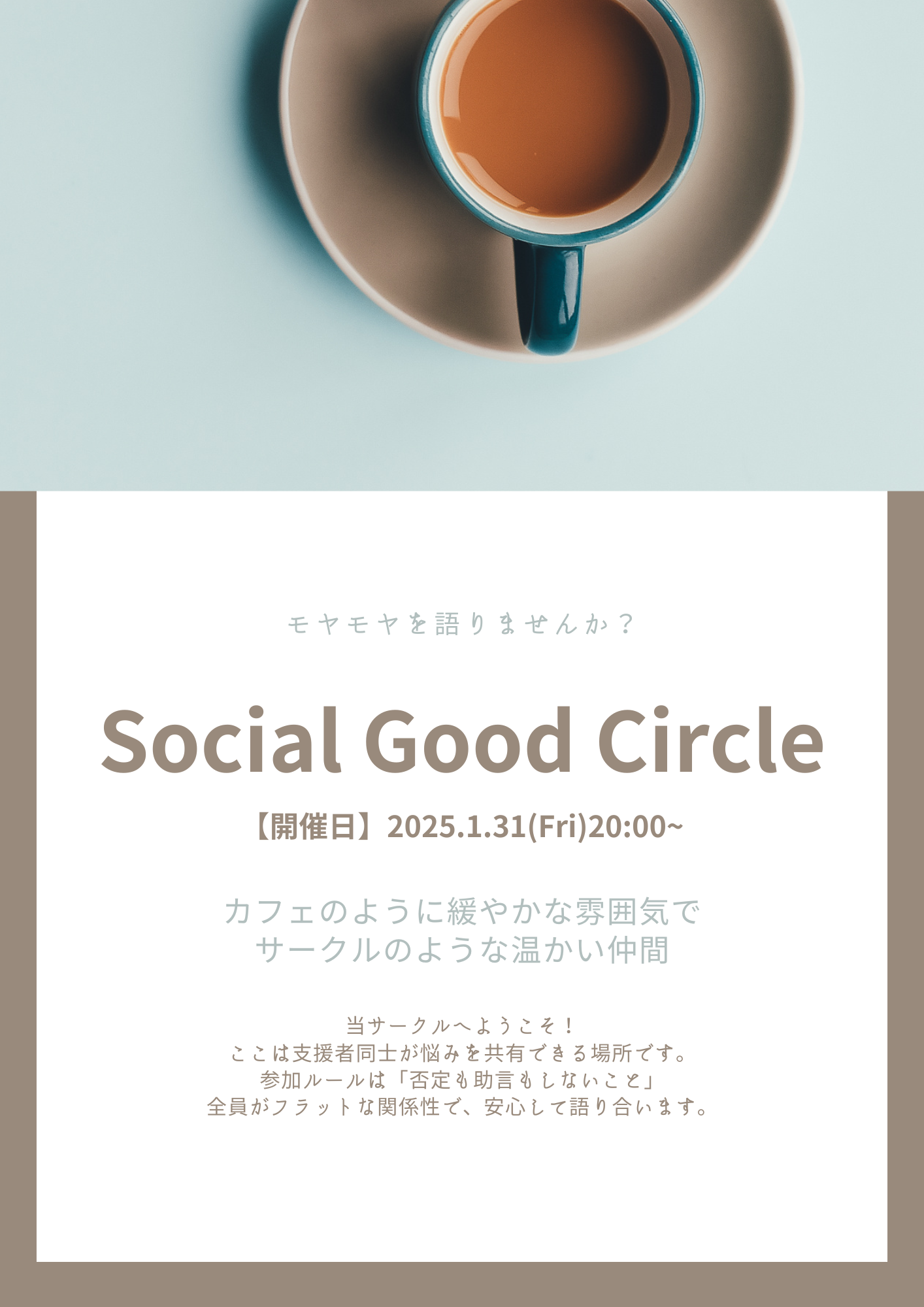
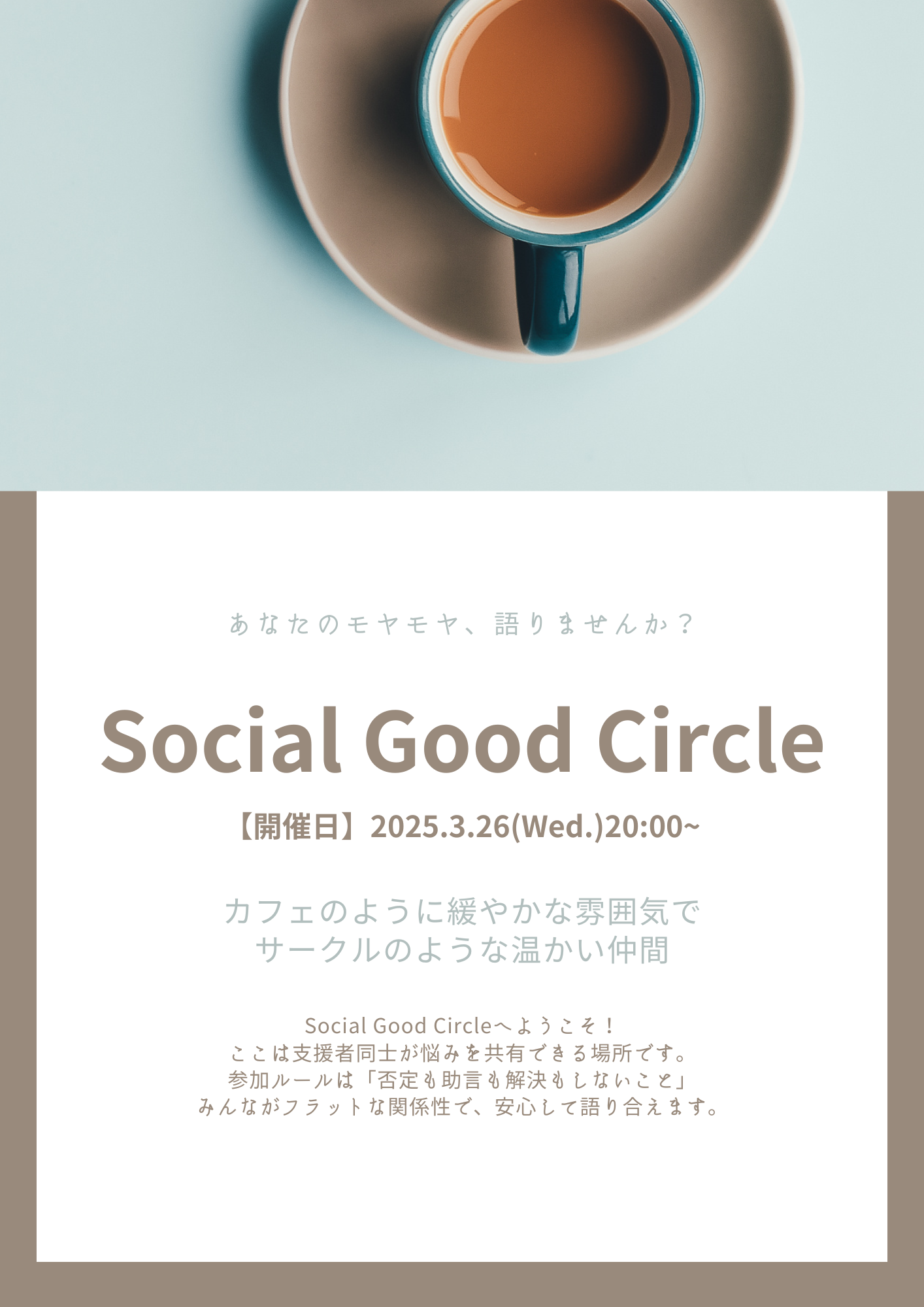
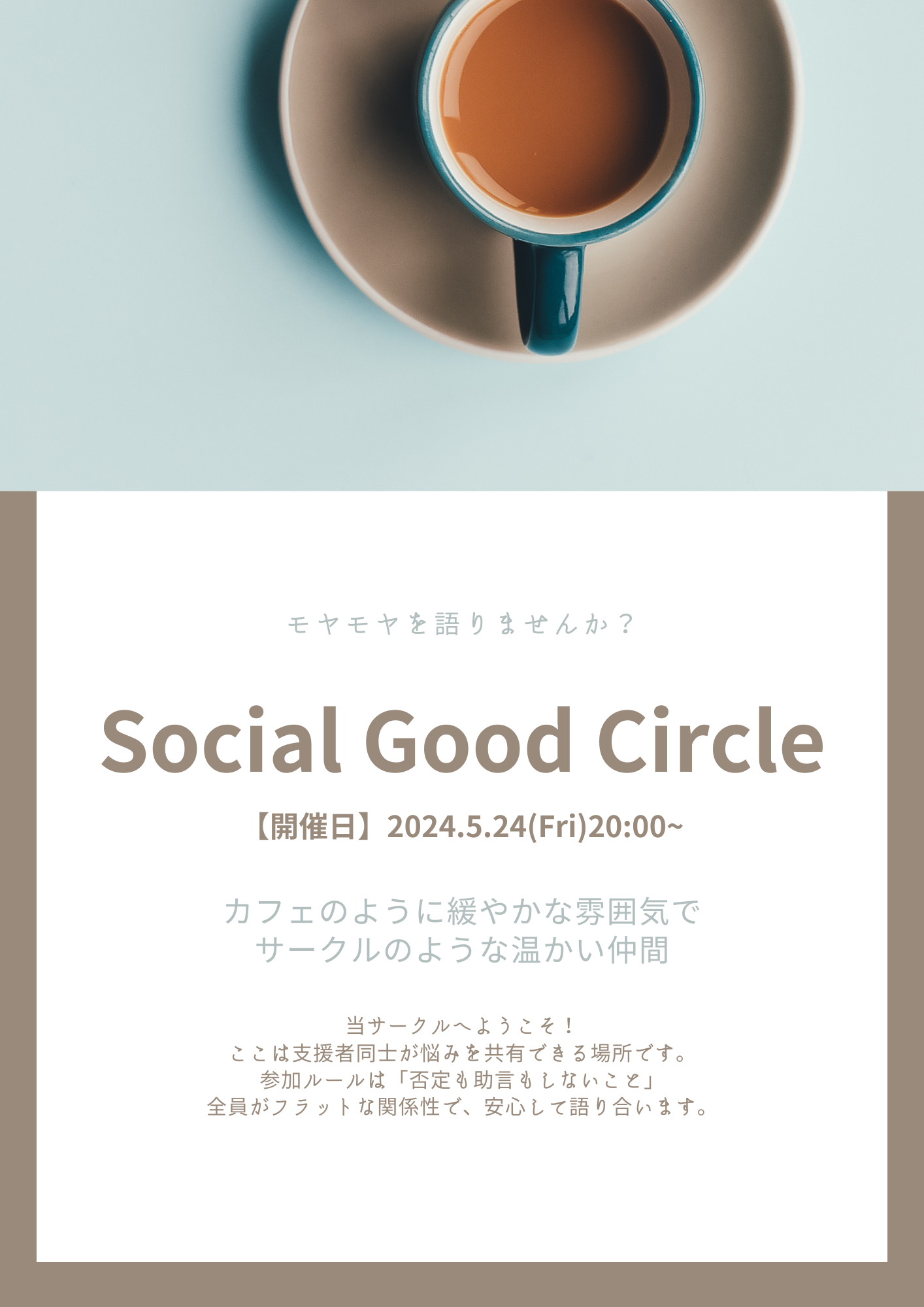
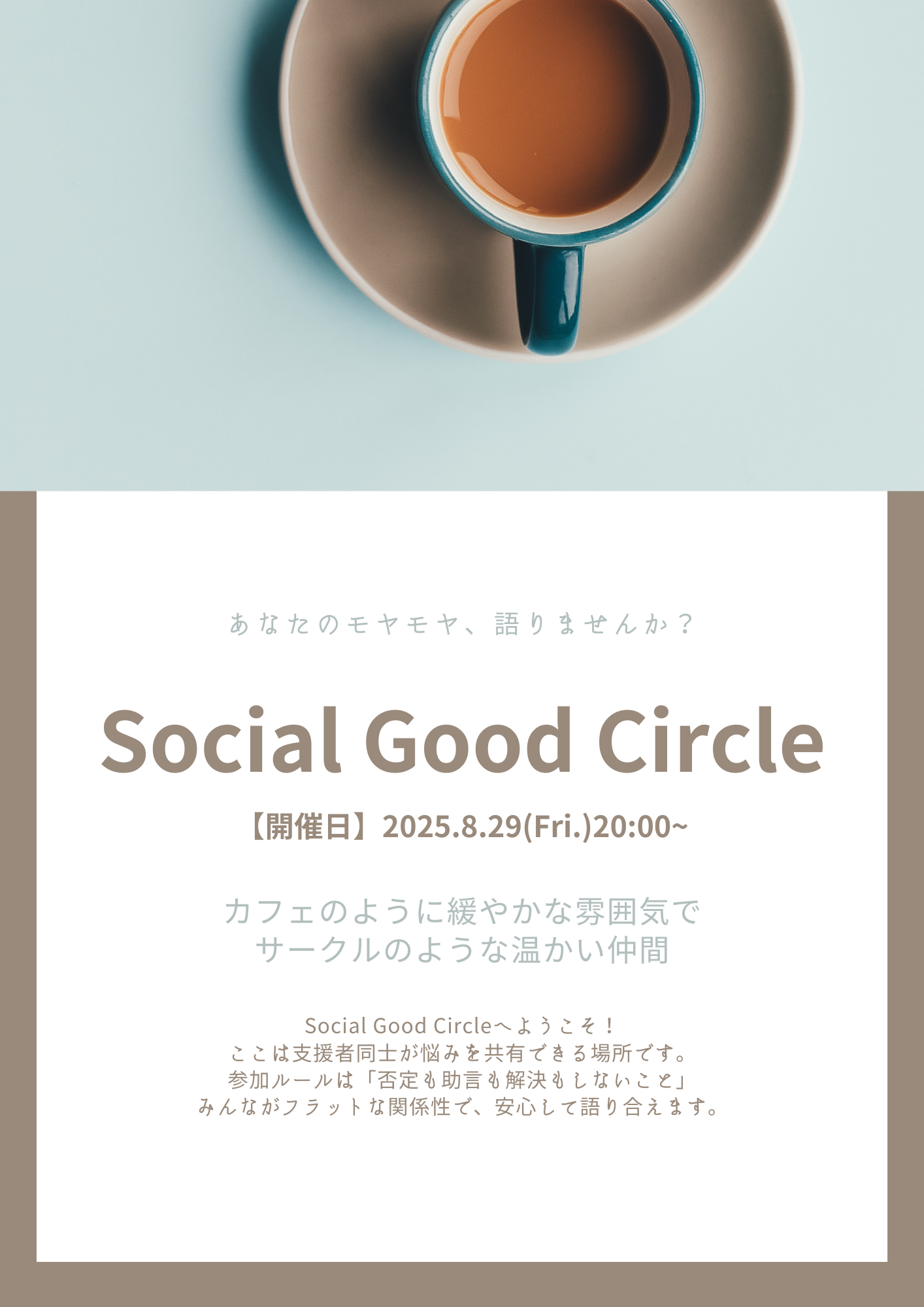
コメント